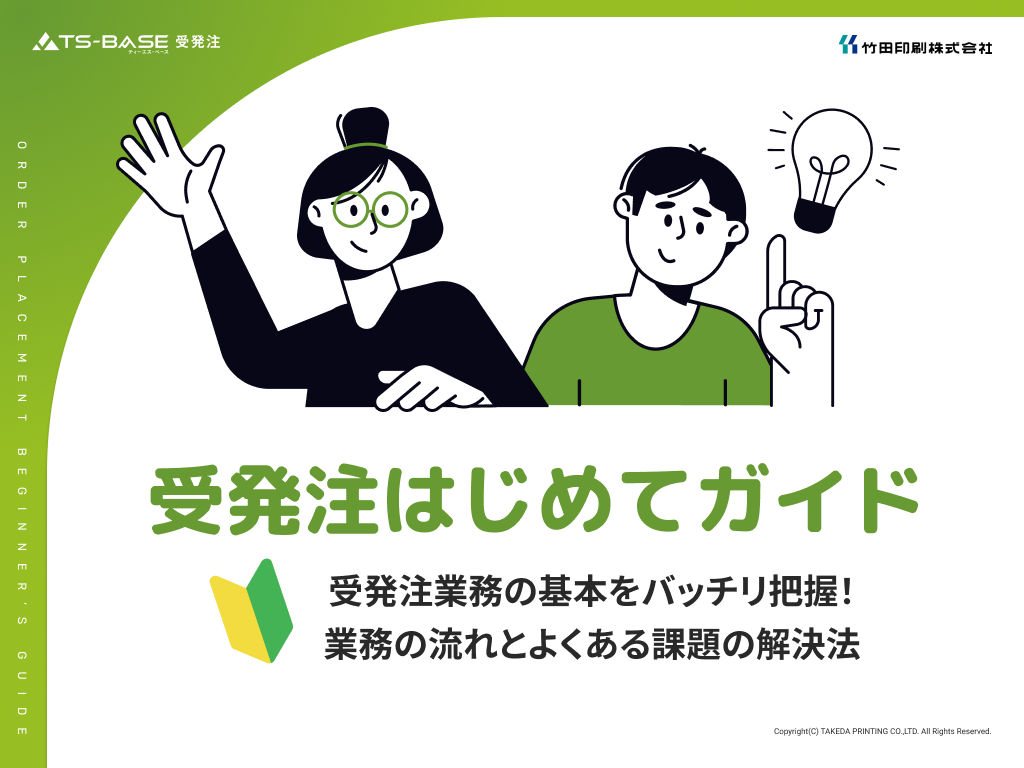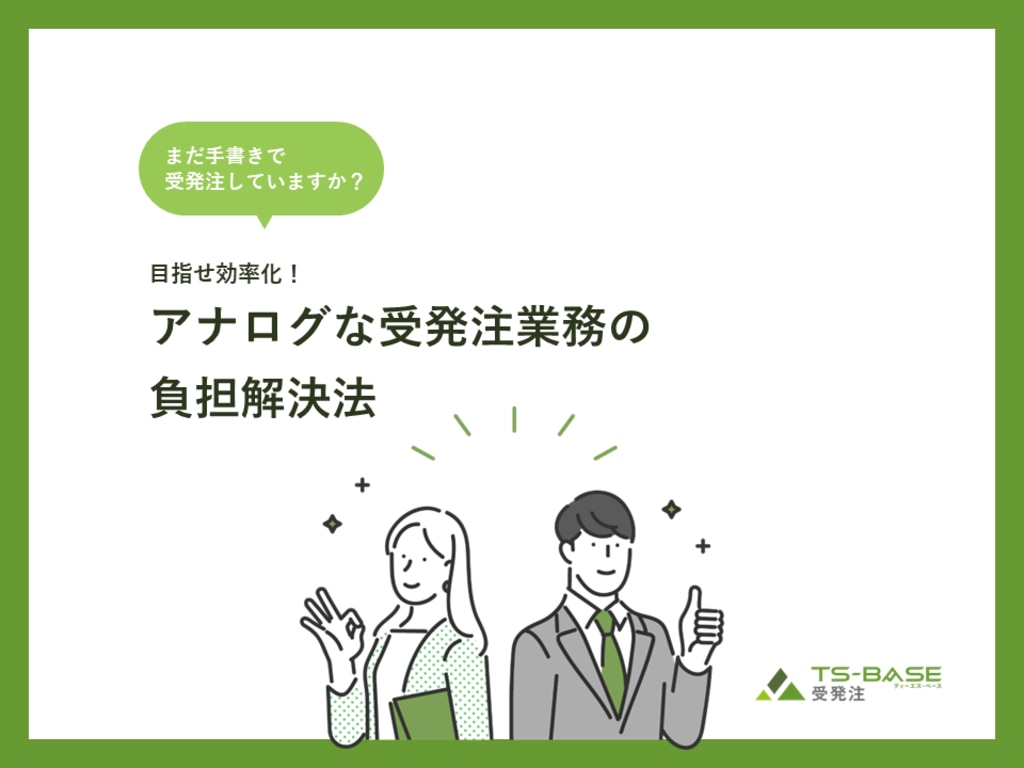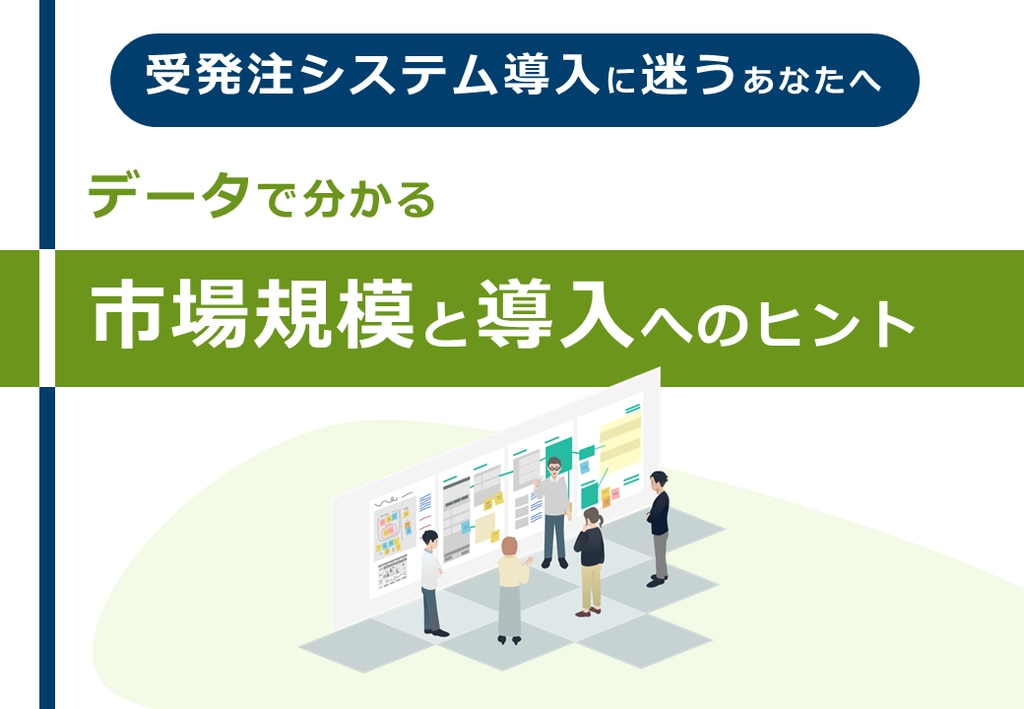製造業・メーカーの生産効率を高める受発注システムのメリットとデメリット
製造業・メーカーにおいて、原料や資材の調達などの物流に関わる受発注業務は現場の効率性やコストに影響する重要な要素の一つです。
電話やFAXで受発注を行っている工場では、「取引先や仕入れ先とのやり取りが煩雑化している」「在庫確認や出荷指示にタイムロスが発生している」といった課題に直面することもあるのではないでしょうか。
これらの課題解決に向けて活用したいのが、受発注システムです。この記事では、製造業における主な受発注業務を踏まえて、システム活用のメリット・デメリットを解説します。
【こちらもおすすめ】
「自社で活用できる受発注システム」を導入するために気を付けたいポイントを解説します。
目次[非表示]
- 1.製造業・メーカーにおける主な受発注業務
- 1.1.1.商品・製品の受注
- 1.2.2.資材・部品の仕入れ
- 1.3.3.荷役・出荷の管理
- 1.4.4.営業所・販売店への輸配送
- 2.製造業で受発注システムを導入するメリット
- 2.1.1.製造リードタイムの短縮
- 2.2.2.在庫欠品や過剰在庫の防止
- 2.3.3.出荷・納品トラブルの防止
- 2.4.4.倉庫や店舗とのリアルタイムな在庫状況の共有
- 3.製造業で受発注システムを導入するデメリット
- 3.1.1.取引先を含めた運用が必要
- 3.2.2.運用定着までに時間がかかる
- 3.3.3.運用コストがかかる
- 4.製造業で活用する受発注システムの選び方
- 5.製造業・メーカーに合った受発注システムで生産性を向上
製造業・メーカーにおける主な受発注業務
製造業・メーカーで取引先や仕入れ先との間に発生する主な受発注業務は以下の4つです。
1.商品・製品の受注
商品・製品の受注業務は、製造や出荷につながる最初の業務です。取引先と見積書や注文書をやり取りし、注文を受け付けます。
2.資材・部品の仕入れ
商品の製造に必要な原料や資材、部品を外部から仕入れる業務です。
生産計画や在庫状況に応じて仕入れ先へ発注を行います。見積書や発注書をはじめとしたさまざまな書類を取り交わすため、煩雑になりやすいのが特徴です。
部品製造時の資材発注に受発注システムを利用している企業様の事例はこちらです。
3.荷役・出荷の管理
出荷指示があった商品を適切に納品するために、荷役・出荷の管理を行います。
工場で製造された商品をそのまま仕分けて出荷する場合と倉庫からピッキングして出荷する場合があります。工場や倉庫、取引先とのやり取りが発生するため、受発注情報や進捗状況の共有が不可欠です。
出荷管理について詳しくは、こちらもご覧ください。
出荷管理とは? 主な業務内容と効率化するための3つのポイント
4.営業所・販売店への輸配送
自社工場で生産した商品を営業所や販売店といった拠点に輸送します。
輸配送の業務は大きく2つに分けられます。
〈社内物流〉
工場で生産した商品を倉庫や自社店舗、営業所(拠点)に輸送する業務。工場と倉庫、店舗間において出荷内容や在庫状況の共有が必要です。
こちらでは、本部と店舗間での受発注業務改善に成功した事例を紹介しています。
〈販売物流〉
生産した商品を卸売業者や小売店、消費者に販売する場合の輸送する業務。配送先への輸送業務に加え、住所や日時などの配送管理が必要です。
製造業で受発注システムを導入するメリット
製造業・メーカーでの受発注業務には、取引先・仕入れ先とのやり取りをはじめ、荷役や輸配送といった物流業務も発生します。これらの業務を電話やFAXで対応している場合は、やり取りの工数が増え、業務が煩雑化しやすいのが特徴です。
受発注システムの導入により、以下のようなメリットが期待できます。
1.製造リードタイムの短縮
受発注システムを活用することにより、Web上での受発注が可能です。注文の受領や資材・部品の調達、出荷指示などに要する工数を削減できるため、製造のリードタイムを短縮し、生産性の向上につなげられます。
リードタイムに関しては、こちらの記事でも詳しく解説しています。
リードタイムとは?種類や計算方法、短縮のポイントについて解説
2.在庫欠品や過剰在庫の防止
受発注システムの利用により、データにもとづく正確な発注処理と在庫管理が可能です。
受注から出荷までの一連の流れをデータ化し、受発注の傾向を知ることで在庫欠品や過剰在庫を防いだ安定的な生産・出荷を実現できます。
3.出荷・納品トラブルの防止
製造業における受発注業務では、複数の取引先ごとに異なるシステムを使用して受発注を行っているケースもあります。商品の個数や単価、納期などのデータ管理が煩雑化するため、処理漏れや確認ミスといった人的エラーが生じやすくなります。
受発注システムを活用することにより、同一システムで顧客ごとの受発注状況を可視化できるようになります。人的エラーを防ぎ、誤出荷や遅延などのトラブルを防止することが可能です。
4.倉庫や店舗とのリアルタイムな在庫状況の共有
受発注内容や出荷状況、在庫状況などをリアルタイムで共有することも可能です。
電話やFAXで受発注を行う場合、倉庫や店舗との間にタイムラグが発生します。特に、店舗と本部で休日が異なる場合にはFAXやメールでのやり取りがスムーズにいかないことも考えられます。場合によっては必要な生産や出荷対応ができず、欠品や余剰在庫が発生する可能性もあります。
受発注システムを活用することで、受発注内容や出荷状況、在庫状況などをリアルタイムで共有できるため、適切な仕入れや生産が可能になります。また、24時間いつでもWeb注文ができるため、電話やFAXによるやり取りも削減。業務効率化を実現できます。
製造業で受発注システムを導入するデメリット
現場の効率化や在庫状況共有の円滑化につながる受発注システム。導入する際は、デメリットについても理解しておく必要があります。
1.取引先を含めた運用が必要
受発注システムは、自社だけでなく取引先・仕入れ先のオペレーションフローも一部変更が必要な場合もあります。電話やFAXによる商慣習が根付いている場合は、オペレーションの変化が足かせとなり、導入に踏み切れない企業もあるでしょう。
システムを導入するには、双方が得られるメリットを伝えたうえで、取引先や仕入れ先に理解を得ることが重要です。導入前にルールやフローについて認識を共有しておくことも重要です。
2.運用定着までに時間がかかる
受発注システムの導入によって業務体制が変化するため、システムの操作や業務フローに慣れるまでに時間がかかることがあります。早期定着化を図るためには、以下のような対応が必要です。
- 社内研修の実施
- 操作マニュアルの作成
これらの対応を講じることで、業務体制の変化による現場の混乱を防ぎ、スムーズに運用を進められます。
3.運用コストがかかる
受発注システムの多くは導入コストや月額料金が発生します。システムによって料金体系が異なるため、自社に必要な機能、受発注件数、業務体制などを考慮して選ぶことが重要です。
なお、システム導入では一定のコストを負担しなければなりませんが、業務効率化や生産性向上によってこれまでにかかっていた人件費や固定費などのコストを削減できるケースもあります。そのため、将来的な費用対効果を踏まえてシステムの導入を検討することが大切です。
製造業で活用する受発注システムの選び方
受発注システムを選ぶときには、自社の課題や導入コストを考慮しつつ、製造業に必要な機能を備えているか確認しましょう。
▼受発注システムの導入でチェックしておきたい項目
- 出荷状況や在庫情報を管理できるか
- 工場と本社、店舗、取引先とリアルタイムに在庫状況を共有できるか
- 倉庫管理や物流に関わる機能が備わっているか
受発注システムの選び方や必要な機能は、こちらも参考にしてください。
BtoB事業者間で活用できる受発注システムの種類と導入手順、必要な機能を解説

受発注管理システムの『TS-BASE 受発注』には、これらを実現する機能が備わっています。
受発注の機能に加えて、倉庫管理システムも備わっているため、出荷状況や在庫情報の管理も可能です。注文データや出荷データを用いて「あと何週受注できるか?」といった受注可能週数を把握できます。週単位だけではなく、毎日・毎週・指定日の状況に応じて算出できるため、適切な生産計画の策定にも役立つでしょう。製品の製造過多や欠品を防止して収益性や安全性を高められます。
また、どの注文者がどれくらい製品を注文したのかや、注文に対する出荷状況なども管理画面からリアルタイムで確認することができるため、業務効率化が期待できます。
TS-BASE 受発注を導入いただいた住宅設備メーカーさまでは、年間1,000万円のコスト削減と⽋品率低下による販売機会の向上効果が得られています。
▼詳しくは、こちらをご覧ください。
製造業・メーカーに合った受発注システムで生産性を向上
製造業・メーカーの受発注業務には、見積書や注文書のやり取りをはじめ、仕入れ、物流などさまざまな業務が発生します。
電話やFAXなどによる煩雑なやり取りを効率化し、生産効率を高めるためには、受発注システムの活用が有効です。
自社の課題や導入コストを踏まえて、製造業に必要な機能が備わった受発注システムの導入を検討してみてはいかがでしょうか。