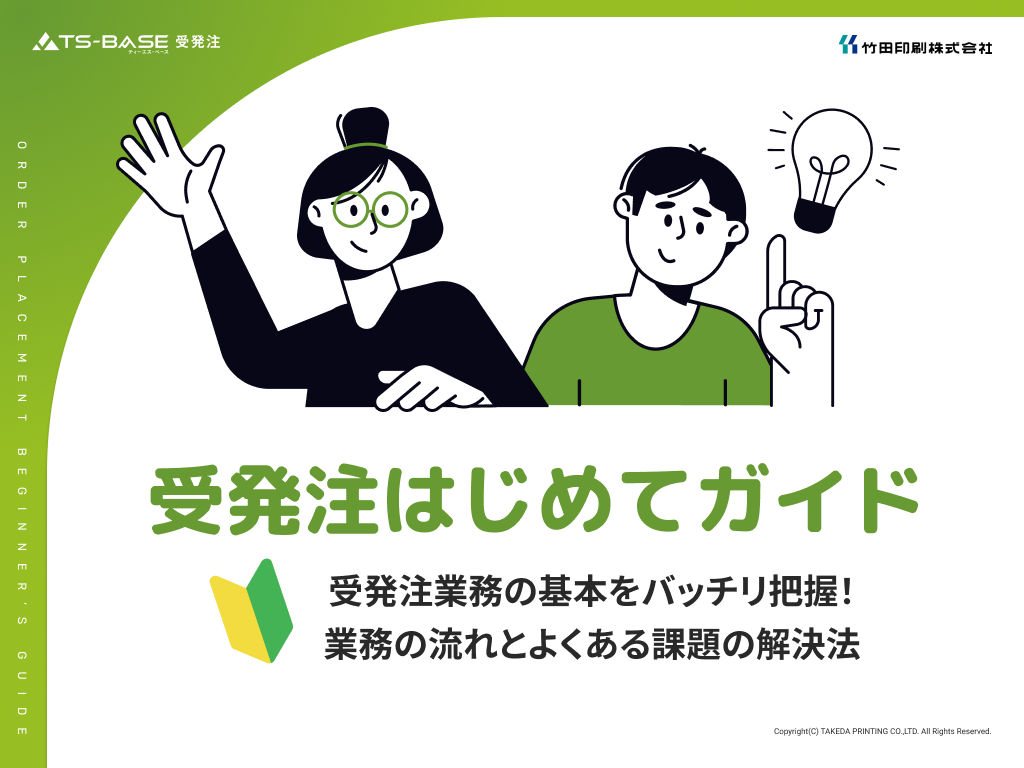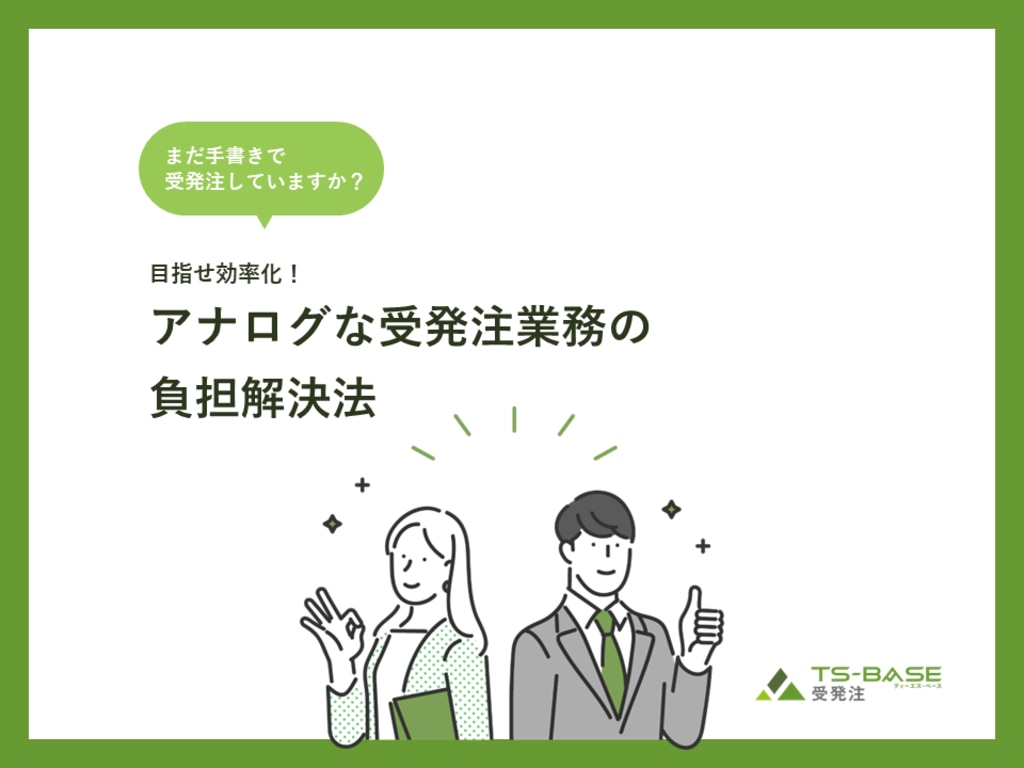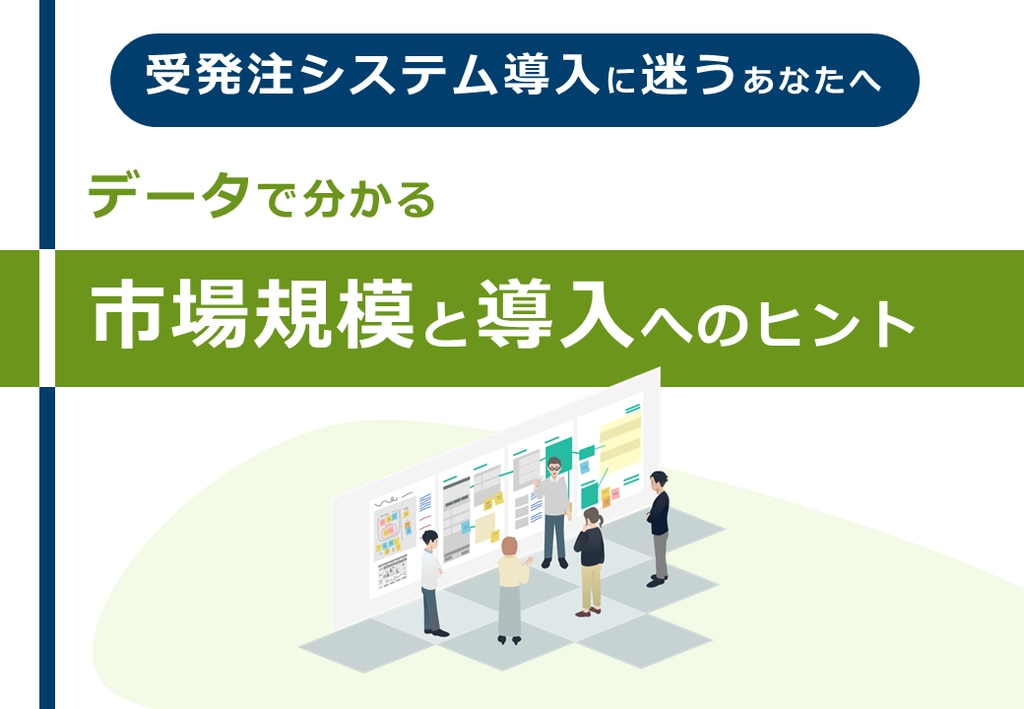受発注システムで業務効率化! 注目機能と3つのメリット、導入事例
「受発注業務に手間がかかっている」「手作業の業務でミスが多発している」など受発注業務に課題を抱えている部署もあるのではないでしょうか。
特に、電話・FAX・メールで受発注を行っている企業においてはデータの入力に手間がかかるだけでなく、人的ミスも発生しやすくなります。受発注で発生しやすいミスを未然に防ぎ、効率的に業務を行うためには受発注システムを活用することも一つの方法です。
この記事では、受発注システムの主な機能をはじめ、導入のメリット・デメリット、選定ポイント、導入事例を紹介します。
【あわせて読みたい】販促物の受発注管理にお悩みの方におすすめ!
販促物の管理、できていますか?管理不足が招く問題と解決策の教科書
目次[非表示]
- 1.受発注システムとは
- 2.受発注システムの主な機能
- 3.受発注システムを導入するメリット・デメリット
- 3.1.メリット
- 3.1.1.1.受発注業務を効率化できる
- 3.1.2.2.処理漏れや転記漏れを防止できる
- 3.1.3.3.リードタイムを短縮できる
- 3.2.デメリット
- 3.2.1.1.システム導入にコストがかかる
- 3.2.2.2.取引先に同意を得る必要がある
- 3.2.3.3.システムに慣れるまで時間がかかる
- 4.受発注システムの導入がおすすめな企業
- 4.1.受発注業務の負荷が大きい
- 4.2.誤受注・発注が多い
- 4.3.業務フローが属人化している
- 5.受発注システムの選定ポイント
- 5.1.1.費用対効果
- 5.2.2.システムの操作性
- 5.3.3.既存システムとの連携
- 5.4.4.受発注データの分析
- 6.受発注システムの導入事例
- 7.TS-BASE 受発注で業務効率化とミス削減を実現
受発注システムとは
受発注システムとは、受発注に関する一連の業務を一元管理できるシステムのことです。受発注管理システムとも呼ばれています。
従来の受発注業務では、電話・FAX・メールが利用されていました。しかし、紙伝票のやり取りや社内システムへの手入力が必要になるため、「リアルタイムで確認できない」「転記漏れが発生する」などの課題がありました。
受発注システムを導入すれば、受発注の処理や紙伝票のやり取りをオンライン上で行えるため、注文、在庫確認、請求書発行などの業務効率化が図れます。また、受発注のデータがオンライン上で共有できることで、入力ミス・転記漏れを防いで、スムーズな受発注が可能です。
BtoB向けの受発注システムは、製造業や物流業、飲食業など、幅広い業種で活用されています。
受発注システムの主な機能
受発注システムには、手間がかかりやすい業務や人の手によるミスを未然に防げる機能が備わっています。
1.注文
受発注システムは、パソコンやスマートフォンの画面から注文を行えます。注文の履歴や個数、入庫予定などの管理情報もすべてシステム内で入力します。
2.注文出荷状況の確認
注文内容や出荷状況をリアルタイムに確認できます。商品やユーザーごとにデータを絞り込んで、注文内容を一目で把握することが可能です。
3.注文の訂正
注文内容をシステム上で訂正できます。誤受注を防げるほか、取引先に電話・FAX・メールで訂正の連絡を入れる手間を省けます。
4.データ分析
注文内容や出荷実績、在庫状況などのデータを出力して分析を行うことで、今後の仕入数・コストを検討できます。データの出力タイミングやデータ項目など、ファイル単位で自由に設計が可能です。
5.在庫管理
入出荷データに基づいて、在庫状況がリアルタイムで受発注システムに反映されます。倉庫の在庫が欠品した場合に、自動的に注文受付の停止も行えます。一つずつ在庫を確認する工数が削減できて、無駄のない受発注業務が実現可能です。
6.各種データ出力
出荷実績や注文履歴などのデータを出力して、ほかの社内システムへ連携できます。また、データを出力する際は、受発注システムに蓄積されているデータを詳細な条件で設定することも可能です。月末月初に必要な報告業務の効率化にも貢献します。
7.マスタ管理
注文サイトの商品マスタのメンテナンスやユーザー別で商品の出し分け設定、ユーザーアカウントの登録・更新などが行えます。最終更新日時・更新者、登録時期などが分かりやすい機能です。
なお、竹田印刷が提供する『TS-BASE 受発注』には、上記を含むさまざまな豊富な機能が備わっています。機能の詳しい情報は、こちらをご確認ください。
受発注システムを導入するメリット・デメリット
受発注システムを導入する際は、システムに備わるさまざまな機能によって得られるメリット・デメリットを知ることが重要です。
メリット
受発注システムを導入するメリットには、以下が挙げられます。
1.受発注業務を効率化できる
受発注業務にかかる工数を削減できます。電話・FAX・メールでは、在庫確認やデータ転送などのやり取りに時間を要します。
システムを活用すると、顧客との確認・承認のやり取りをオンライン上で完結することが可能です。これにより、受発注業務が効率化されて、業務負担の軽減、生産性の向上につながることが期待できます。
2.処理漏れや転記漏れを防止できる
受発注システムには、処理漏れや転記漏れを未然に防げるといったメリットもあります。
注文内容や在庫状況は自動で受発注システムに反映されるため、手作業による入力間違い・2重入力・処理忘れなどを防げます。
これにより、誤受注・発注や確認漏れを防止できて、納品トラブルの回避にも役立ちます。
3.リードタイムを短縮できる
受発注システムを導入すると、入出荷状況や在庫数などのデータをリアルタイムで共有できます。
これにより、倉庫管理者に在庫数を問合せたり、紙伝票と照合したりなどの作業が不要になります。
社内の情報共有がスムーズになることで、受注処理や納品までのリードタイムを短縮できるため、サービスの向上にもつながります。
デメリット
受発注システムの導入には、以下のようなデメリットもあります。
1.システム導入にコストがかかる
受発注システムを導入する際はイニシャルコストが必要です。
自社に適したシステム開発を行う場合には、コストが高額になる可能性があります。自社の課題に応じて、必要な機能やプランを選択できるシステムを選ぶことが重要です。
2.取引先に同意を得る必要がある
システムの導入によって受発注の方法が変わるため、事前に取引先の企業に同意を得ておく必要があります。
双方にとってメリットがある点を伝えたうえで、お互いの業務フローを調整するといった配慮も求められます。
3.システムに慣れるまで時間がかかる
システムによっては、操作に慣れるまでに時間がかかるケースがあります。また、これまでと業務フローが変わるため、社内での教育やマニュアル作成も必要です。
なかには導入前後のサポートやデモ環境で操作を体験できるシステムもあります。システムの導入前に使い勝手や自社に合っているかを確認したい場合は、トライアル機能のあるシステムを選ぶことも重要です。
なお、受発注業務を一元管理するメリットについては、こちらの記事をご覧ください。
受発注システムの導入がおすすめな企業
受発注システムの導入を検討している方は、自社の課題を踏まえて導入要否の判断が重要です。
受発注業務の負荷が大きい
受発注業務に関わる一人当たりの負荷が大きい現場では、システムの導入がおすすめです。
電話・FAX・メールで受発注を行う場合、受発注の返信対応や社内システムへの転記、工場や倉庫への進捗確認などさまざまな業務に対応する必要があります。
各対応に必要な人員を配置できていないと、一人当たりの業務量が多くなり、作業が煩雑化する、コア業務にリソースを割けないなどの課題につながります。
受発注システムを活用することで、オンライン上で業務が完結するため、作業やプロセスの削減、業務負荷の軽減が実現します。
誤受注・発注が多い
誤受注・発注がたびたび発生している場合にも、受発注システムの導入が有効です。
電話・FAX・メールでの作業における誤受注・発注には、以下の原因が考えられます。
▼誤受注・発注が起こる原因
- 受発注データの手入力・転記によるミス
- 関係者・現場間での連携不足
データの手入力は、入力ミス・転記漏れなどの人的ミスが発生しやすく、商品名や納期、個数などを誤って注文してしまう可能性があります。
また、受発注業務では、相手企業との連絡だけでなく、工場や倉庫、経理部門など複数の関係者間で情報共有が必要です。情報共有がスムーズでないと、納品日の遅延や在庫不足などの問題が発生しやすくなります。
受発注システムを活用すれば、受発注データや入出荷状況を一元管理して、リアルタイムな連携が可能になるため、トラブルを防げます。
なお、受発注業務のミスが起こる原因と対策については、こちらの記事をご確認ください。
業務フローが属人化している
受発注の業務フローが担当者ごとに属人化している現場では、受発注システムの導入がおすすめです。
属人化すると、特定の担当者が不在の場合に作業が停滞する、業務効率や生産性が低下するといった問題が生じます。また、状況把握に時間がかかったり、データの整合性が取れなくなったりと、さまざまなトラブルが発生する可能性もあります。
受発注システムの導入によって、受発注業務がデジタル化されて、業務フローの標準化が可能です。受発注状況を可視化できるため、社内での業務の引き継ぎや情報共有が円滑になり、担当者以外でも柔軟に対応できるようになります。
受発注システムの選定ポイント
受発注システムにはさまざまな種類があるため、ポイントを押さえつつ、自社の課題や予算に合ったシステムの選定が重要です。
1.費用対効果
イニシャルコストやランニングコストをネックに感じている場合は、現在の業務状況を見直したうえで、導入による費用対効果を考えることがポイントです。
システムの導入によって業務改善が実現すれば、従来の管理体制を省人化する、別の業務に割ける工数を増やせるなどの効果も期待できます。
2.システムの操作性
操作しやすいシステムを選ぶことも大切です。
特に画面やメニューの表示方法、ツールの使い方がシンプルなものが望ましいといえます。スマートフォン・タブレットから手軽に作業できるシステムであれば、別の事業所や自宅からのテレワークにも対応できます。
3.既存システムとの連携
受発注システムには、会計ツールや顧客管理システムなど社内で稼働中の既存システムと連携できるタイプもあります。
システムの連携方式にはさまざまな方法があるため、既存システムがどの方式と連携できるかを事前に確認しておくことが必要です。
なお、システムの提供元によっては、個別のカスタマイズに対応している場合もあります。受発注システムの導入時は、自社の業務プロセスに合わせたカスタマイズの可否を相談してみるのも一つの方法です。
受発注システムを新たに導入する場合には、注文・WMS・管理を一括提供できるシステムもおすすめします。
4.受発注データの分析
分析機能を備えたシステムでは、蓄積された受発注データの分析が可能です。仕入数や原価、在庫評価額などを分析することで、需要予測、さまざまなコスト(製造コスト・保管コスト・廃棄コストなど)の見直しにも活用できます。
なお、受発注システムの選定ポイントの詳細は、こちらの記事をご覧ください。
受発注システムの導入事例
TS-BASE 受発注は、「電話・FAX・メールでの受発注業務の負担が⼤きい」「アナログな在庫管理から脱却したい」などの課題解決に貢献します。
ここでは、実際の導入事例を3つ紹介します。
住宅設備メーカー
住宅設備メーカーにおいて、管理部門と営業所における販促物の管理、受発注業務にTS-BASE 受発注を導入いただきました。
▼導入前の課題
システム導入前には、以下の課題がありました。
- 販促物の分散管理(10拠点)による物流コストの負担
- 出荷依頼方法や受取方法などが各拠点によって異なる
- 販促費振り分けのためのデータ集約・作成に時間を要する
解決するためには、分散管理されている物流コストと、出荷依頼や出荷管理の体制について見直しが必要でした。
▼導入の決め手
システム・ロジスティクス・BPOに精通したスタッフから課題の整理やプラン提案、運用までの細やかなサポートを受けられて、安心感がある点が決め手だったとのことです。
▼導入効果
課題のヒアリングから実運用までトータル3ヶ月で行い、低コスト・スピーディにサービスを稼働しています。
受発注システムの活用で、年間1,000万円、10%強のコスト削減を実現しました。また、注文方法・サービスの一本化、営業所からの問合せ対応の半減(月:約100回から約30回へ)、経費振り分け処理の半自動化により、業務負担を軽減できました。
住宅設備メーカーの導入事例は、こちらからご覧いただけます。
医療用ガス商社
医療用ガス事業を手掛ける商社では、営業課と在宅医療課において、TS-BASE 受発注を導入いただきました。
▼導入前の課題
営業課と在宅医療課の受発注業務において、以下のような課題がありました。
対象 | 課題 |
営業課 | 医療機関・企業からの注文処理に時間・手間を要する 配送拠点との連携に時間がかかり、納期回答が遅れる |
在宅医療課 | 1日100件前後の注文電話の対応に追われる 注文内容の手書きでの転記、FAXでの書類作成の作業が煩雑化している |
注文者・受注者間の情報共有を円滑化して、受注から出荷手配までの業務効率化を図る必要がありました。
また、テレワーク推進の観点からも、受注業務の多様化を図ることが必要でした。さらに、社会情勢の変化や災害時でも安定的な受発注に対応するため、環境に左右されないフローの構築も求められていました。
▼導入の決め手
導入の大きな決め手は、「利便性と課題解決に直結する提案をしてくれたこと」が挙げられています。競合他社では検討してもらえなかったオリジナル機能の追加について、熱心に話を聞いてもらえたこと、複数のカスタマイズを提案してもらえたことが理由です。
▼導入効果
以前は多くの工数がかかっていた配送予定表の作成時間が、大幅に削減できました。“企業仕様のVBAツール”機能を追加したことで、作業時間の3割削減を体感されています。
注文者・受注者間のミスコミュニケーションが削減されたほか、電話対応による、ほかの業務の遅延改善にも貢献しています。また、タブレットやスマートフォンなどを利用して遠隔で注文できるため、顧客満足度にもつながっています。システムの使いやすさも担当者から好評です。
なお、医療用ガス商社の導入事例は、こちらからご覧いただけます。
【あわせて読みたい】
印刷・同関連業
BtoB向けのフォトブックサービスを提供している企業では、顧客へ配布するサンプルブックの受発注業務と入出庫管理業務において、TS-BASE 受発注を導入いただきました。
▼導入前の課題
システム導入前には、以下の課題がありました。
- 56種類あるサンプルブックの在庫数を目視で確認
- 注文後のやり取りが頻繁に発生して工数がかかっている
- 注文内容管理、在庫管理、入出庫管理などの項目別でツールが分かれており、ツールをまたいでの同情報入力やデータの更新漏れなどが負担だった
▼導入の決め手
導入の決め手は、課題解決に必要な“注文から注文内容確定までの工数削減”と“一連の管理業務の効率化・利便性向上”が実現できそうなシステムだったことが挙げられます。
▼導入効果
TS-BASE 受発注を導入して、受注から出荷までの5工程が3工程に削減されました。
▼導入前後の業務フローの違い
導入前 | 導入後 |
|
※在庫確認と受注処理の工程を、TS-BASE 受発注で対応している |
TS-BASE 受発注を介して、受注処理を行うほか、注文データがオンライン上に自動で反映されて担当営業とのやり取りや在庫確認作業の削減を実現しています。また、受注から出荷までの作業時間も、約40分から約20分に抑えられています。
印刷・同関連業の導入事例は、こちらからご覧いただけます。
TS-BASE 受発注で業務効率化とミス削減を実現
受発注システムを活用することで、商品名や個数を手入力する作業が不要になり、人的ミスを未然に防ぎながら受発注業務の効率化が可能です。また、相手方との確認・承認作業や、社内での情報共有もスムーズに行えるため、リードタイムの短縮化、業務フローの標準化にもつながります。
「受発注に関わる業務を一括管理したい」「人的ミスを減らしたい」という担当者さまは、『TS-BASE 受発注』の導入を検討してみてはいかがでしょうか。
受発注業務の業務効率化に役立つ資料は、こちらからダウンロードいただけます。ぜひ併せてご覧ください。
なお、クラウド型受発注システムの概要やクラウドにできることについては、こちらの記事で解説しています。