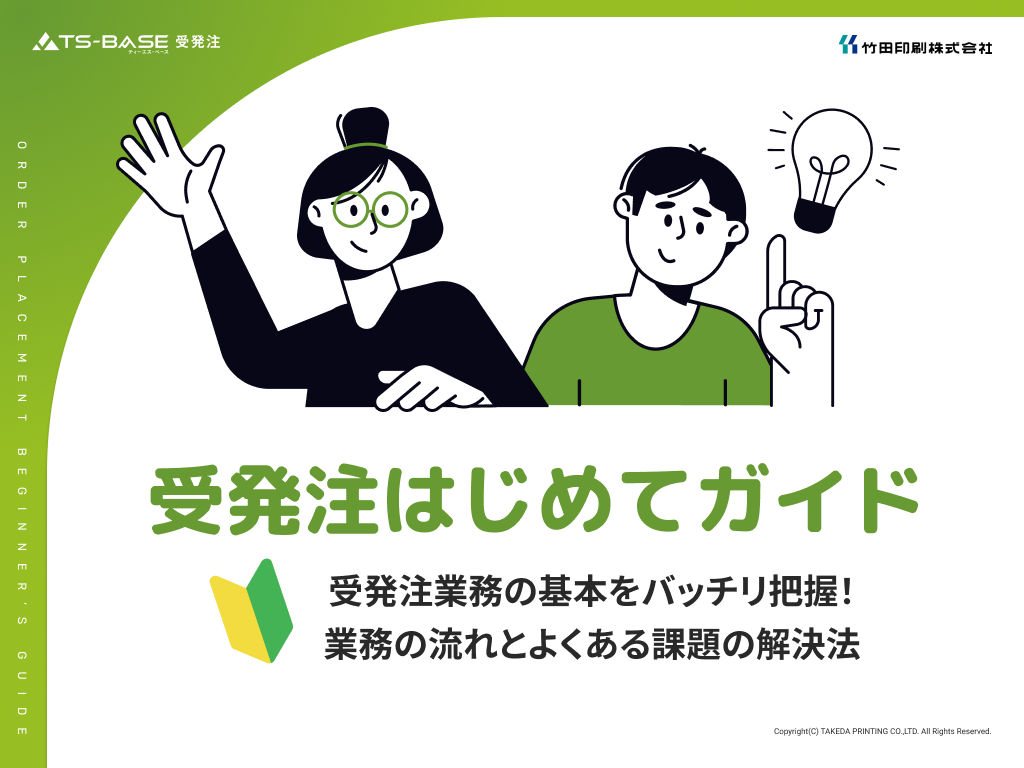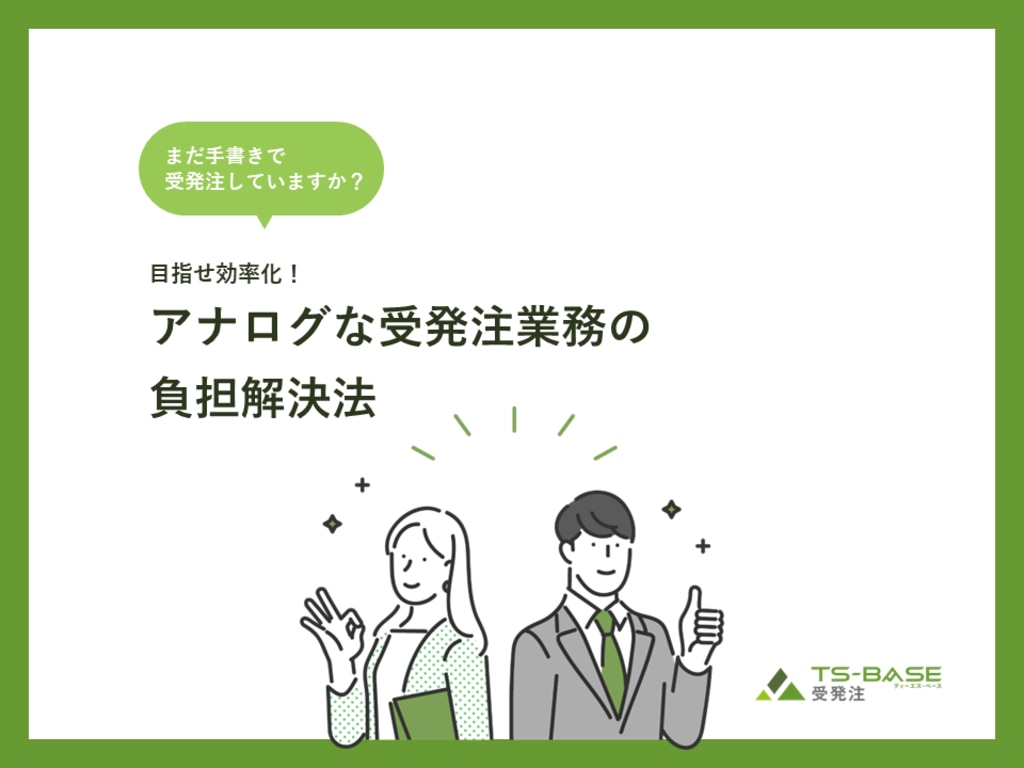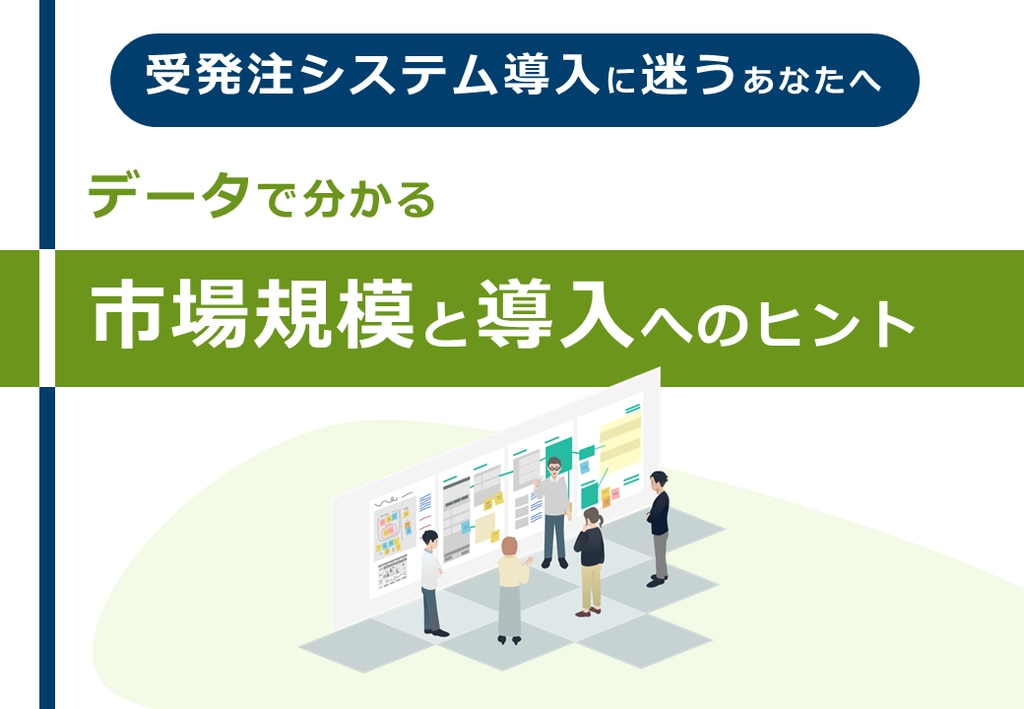EDIとは。3つの種類とデジタル化を実現するWeb-EDIのメリット
物流や小売などの業界では取引先とのやり取りから在庫の管理、発送業務などの取引業務が発生します。特に、紙面でのアナログな手法で業務を行っている場合、人的ミスが起こりやすいことや業務が煩雑化しやすいことが課題です。
煩雑な取引業務を効率化するために有効なのが、EDI(電子データ交換)やEOS(電子発注システム)です。EDIやEOSは主にBtoBでの取引をスピーディかつ効率的に行うために用いられています。
企業の管理部門の担当者のなかには、「EDIとはどのようなものなのか」「業務をデジタル化して効率化するにはどうすればよいのか」などと気になる方もいるのではないでしょうか。
この記事では、EDIの概要や種類、EOS・BMSとの違い、Web-EDIの特徴について解説します。
▼こちらもおすすめ
目指せ効率化! アナログな受発注業務の負担解決法
目次[非表示]
- 1.EDIとは
- 2.EDIと混同されやすいEOSやBMSとの違い
- 3.EDIの種類
- 3.1.EDI
- 3.2.インターネットEDI
- 3.3.Web-EDI
- 4.現在はブラウザベースのWeb-EDIが主流
- 5.受発注業務のデジタル化は『TS-BASE 受発注』で対応可能
EDIとは
EDIとは“Electronic Data Interchange”の略で電子データ交換を意味します。
具体的には納品書や受領書、請求書などのやり取りをインターネットまたは専用回線を通じて行うシステムを指し、主にBtoBでの受発注業務に利用されています。
EDIを用いて企業間で専用回線を通じて電子データをやり取りすれば、かかっていた工数を削減できます。また、納品書や請求書などを発行する必要がないため、受発注業務の効率化や人的ミスの防止などのさまざまな効果が期待できます。
新型コロナウイルス感染症の拡大を契機にしたテレワークの普及や、社会におけるDXの推進を背景として、電子データをやり取りするEDIの活用も広がっています。
EDIと混同されやすいEOSやBMSとの違い
EDIと混同されやすい用語にEOSとBMSがあります。EDIとの違いは以下のとおりです。
▼EDIとEOS・BMSの違い
用語 |
概要 |
EDI |
企業間取引全般を電子データでやり取りする仕組み・システム |
EOS |
受発注業務に特化してデジタル化するシステム |
BMS |
流通事業者が用いるEDIの標準仕様・ガイドライン |
EOSは受発注業務のデジタル化に特化しており、EDIが持つ機能の一部にEOSが含まれているといえます。
また、BMSはEDIの電子取引文書のフォーマットを統一して、企業間のデータ連携を効率化・最適化するためのガイドラインを指します。
EDIの種類
EDIには、使用する回線や通信の手法によって複数の種類が存在します。
EDI
従来のEDIでは、固定電話回線を利用して通信を行います。
また、取引先を識別するための識別コードや、CSV形式・固定長形式などのデータ形式が異なる3つの区分があります。自社の環境や取引に応じて選ぶことが重要です。
▼識別コードやデータ形式によるEDIの区分
区分 |
特徴 |
個別EDI |
|
標準EDI |
|
業界VAN |
|
インターネットEDI
インターネットEDIとは、インターネット回線を利用したEDIのうち、標準化された通信手順を使用するものです。電話回線を使用する従来のEDIと比較して通信速度に優れます。
また、通信手順や仕様が標準化されていることから、さまざまな取引先とのやり取りが行いやすい点も特徴です。
Web-EDI
Web-EDIとは、インターネット回線を利用したEDIのうち、Webブラウザ上で取引を行うものを指します。専用のソフトウェアを必要としないことから、導入しやすい点が特徴です。
ただし、Web-EDIはインターネットEDIと異なり通信手順が標準化されていないため、システムの互換性がない取引先とやり取りする場合には個別に対応する必要があります。
なお、Web-EDIの概要や通信プロトコルについては、こちらの記事で詳しく解説しています。併せてご確認ください。
Web-EDIの導入時に重要となる通信プロトコルの種類と特徴
現在はブラウザベースのWeb-EDIが主流
EDIにおいては、ブラウザベースのWeb-EDIが現在の主流となっています。
従来のEDIに使用されていた、固定電話回線によるデジタル通信網サービスが2024年1月に終了しました。2027年頃までは補完策としての通信サービスが提供されるものの、通信の速度や安定性に影響する可能性があります。
そのため、従来のEDIからの乗り換え先として、導入が行いやすいWeb-EDIを選択する企業が見られます。Web-EDIを業務に導入することで、以下の効果が期待できます。
出典:総務省『固定電話のIP網への移行に向けた取組み状況について』
業務の効率化
Web-EDIを活用することで、業務の効率化が可能です。
従来のEDIと同様に納品書や請求書を紙面でやり取りする必要がないため、ペーパーレス化による業務の効率化が可能です。
また、Web-EDIはブラウザが使用できればパソコンでなくモバイル端末でも利用できることから、業務フローの効率化にもつなげられます。
通信の高速化
固定電話回線を使用する従来のEDIからWeb-EDIに切り替えると、インターネット回線を利用できることで通信の高速化が実現します。
高速通信によって通信にかかる時間が短縮されるため、大容量のデータをやり取りする取引であっても効率的に行えるようになります。
コストの削減
Web-EDIを業務に導入することで、コストの削減が期待できます。
納品書や請求書などのペーパーレス化は、紙やインクにかかる経費の削減につながります。
また、Web-EDIはほかのEDIと比較して専用の回線やソフトウェアなどを必要としないため、導入時に発生するコストも抑えやすいといえます。
受発注業務のデジタル化は『TS-BASE 受発注』で対応可能
受発注に関するやり取りをデジタル化するには、Web-EDIを活用するほかに受発注システムを活用することも一つの方法です。

受発注システムを導入すると、ペーパーレス化によって受発注業務にかかる工数を削減できます。処理漏れや転記漏れの防止も可能です。
『TS-BASE 受発注』では、注文者・受注者・仕入先の3者をつなぐ、営業事務に適した受発注システムの機能を提供しています。注文者や仕入先とのやり取りをシステム上で完結できるため、受発注フローの効率化とスピードの向上を図れます。
TS-BASE 受発注の詳細については、こちらの資料をご確認ください。