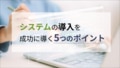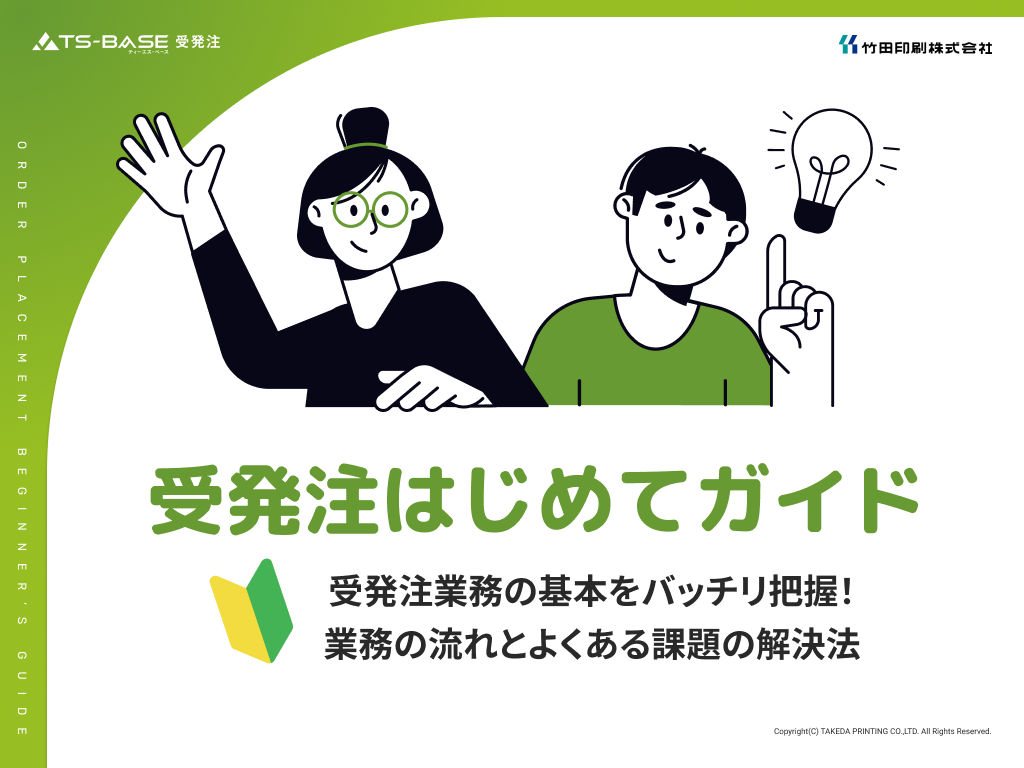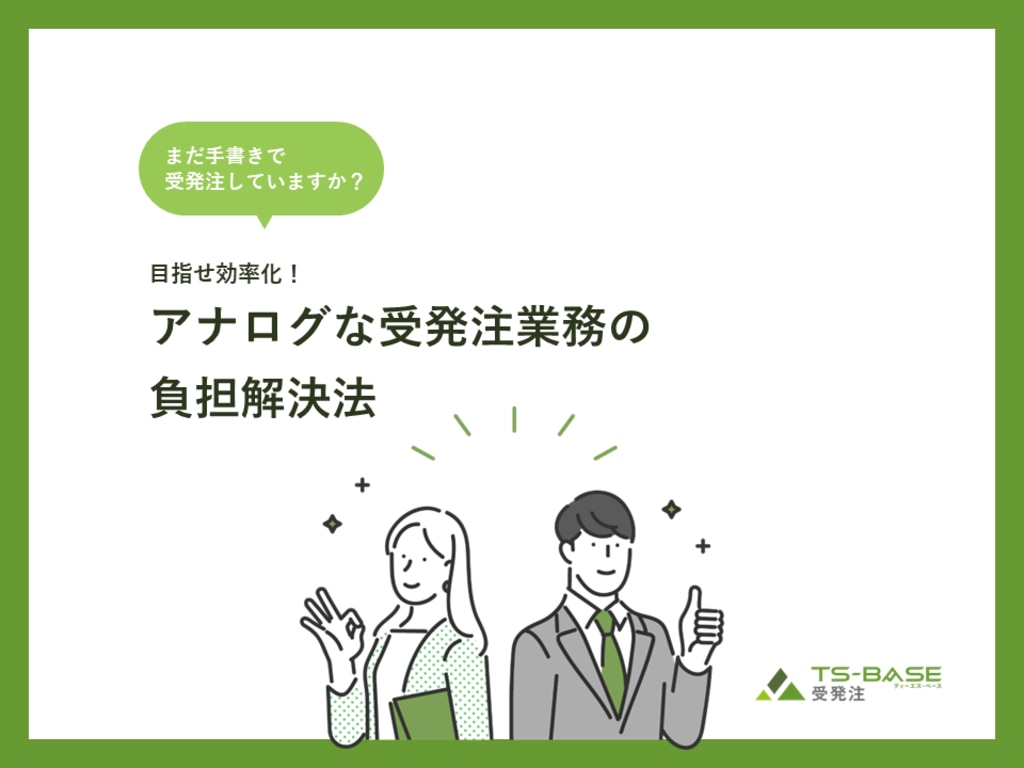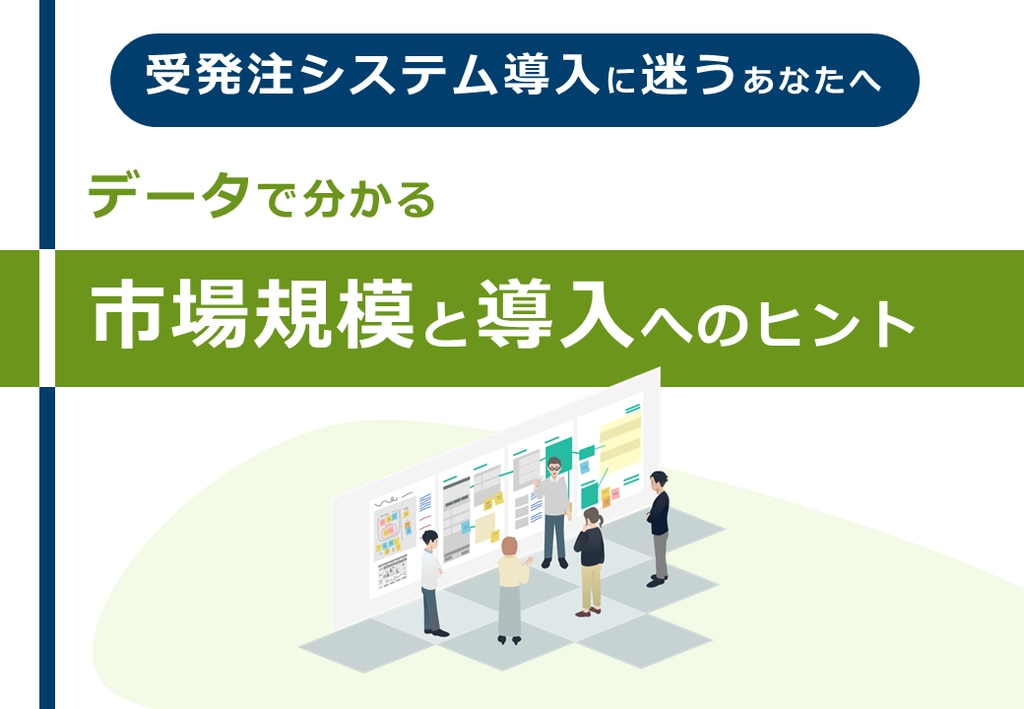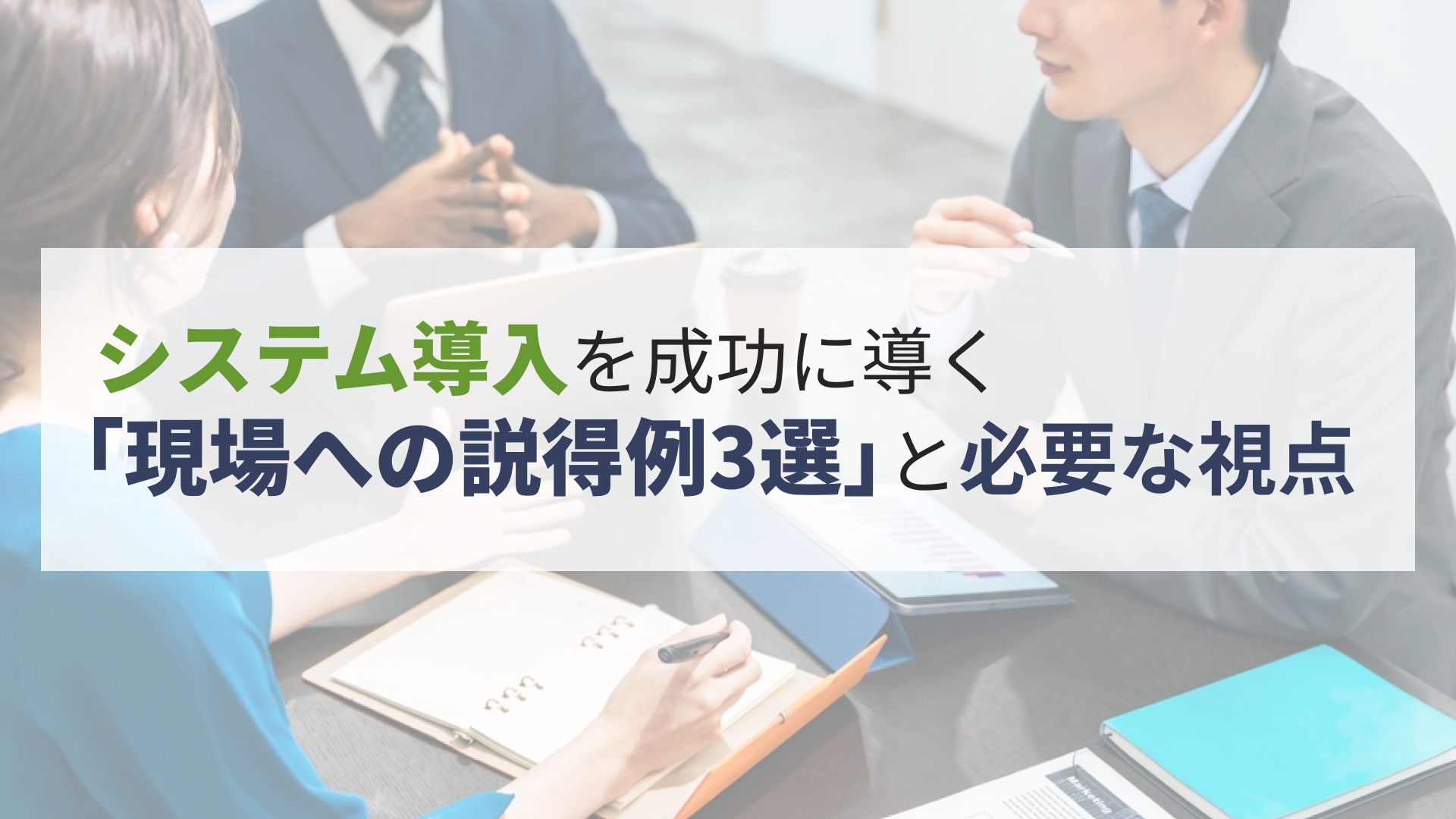
システム導入を成功に導く「現場への説得例3選」と必要な視点
マイナスイメージを払拭して、システム導入を円滑に進めよう!

システムを新たに導入する際に発生するハードルの一つに「周囲からの理解」があります。明確な「嫌な理由」を伴うハードルもあれば、今までの業務方法を変えることが、「なんとなく嫌」という理由なき拒否反応がハードルになっている場合もあります。
少しの不便があったとしても、業務は回っているという状況を天秤にかけると「今のままでよいのでは?」という現状維持を選択したくなります。これは、未知の状況に対する不安やリスク回避の心理が働くため、「変えることで悪化するかもしれない」という恐れが、変化への抵抗につながっていることが予測されます。
慣れ親しんだ環境や行動パターンの変化は、ストレスやさまざまな消耗を伴う可能性があるため、避けようとするのは人間らしい行動です。このようなハードルを理解した上で、不安をクリアし、「新しいシステムを活用して業務を行おう!」と、前向きになってもらうには、正しい情報を適切に提供して認知してもらうことが大切です。
発生するハードルに対して生じる「あれどうするの?」という疑問は数多くあります。その中から、受発注担当者から出やすい3つをクローズアップし、その解決案をご紹介します。
アナログな受発注業務を自動化することで、作業負担の軽減や業務の標準化につながります。
アナログな受発注業務を自動化するメリット
発生しやすい3つの疑問と説得例
受発注に限らず、業務の現場メンバーは多くのトラブルから学び、回避する工夫を施して業務を行っています。それが故に、業務内で注意すべき特定のポイントにフォーカスをした疑問が出る確率が大いにあります。一つ一つ丁寧に解決することで、システム導入担当者にとっても新たな気付きを得るきっかけにもなるでしょう。
①「システムを導入することで、今より面倒になるのでは?」

現運用の作業量や負荷の予測は容易です。たとえ手間がかかっていたとしても、その範囲内で効率的にリソースを配分して業務をこなしてきた実績もあります。そこへ、「システムを導入しようと思う」と言われたら、受注担当者は「ただでさえ忙しいのに、余計大変な…」と、先入観だけでマイナスなイメージを抱いてしまうことは珍しくありません。
実際に、ある企業のシステム導入担当者が受注現場に相談をした際、このようなことを言われたそうです。
「メールやFAXなら、前回の数字を書き換えればいいから楽だけど、システムにしたらログインして選んで入力して…とか手間が増えるでしょう?」(受注担当者)。
受注現場で工夫をしている一場面を例にシステムへの嫌悪感を伝えてきた現場担当者に対し、システム導入担当者は、このように返答しました。
「ログインの手間は増えるかもしれないけど、以前の発注データを再利用した注文もできるし、複数の制御機能もあるから、“やっぱりこうしたい!”という顧客からの突然の方針転換も少なくなりますよ」(システム導入担当者)。
受注担当者の疑問と不安を解消することで、前向きに対話を進めることができます。また、上記の例のように、スポット場面で嫌悪感を抱く場合も多いので、その疑問を解決しつつ、「業務全体でどのような変化があるのか・効率化できるのか」も丁寧に説明(アピール)する必要があります。
受発注システムの導入によって得られる具体的なメリットや事例については、以下の記事をご覧ください。
受発注システムで業務効率化! 注目機能と3つのメリット、導入事例
②「余白に書いていたコメントはどうなるの?」(特殊ルール)

FAXやメールでの注文でありがちなのが、顧客ごと「〇〇の時はココに注釈を入れる」などの「特殊ルール」が点在しているパターンです。共通フォーマットはあるものの、「項目として追加するほどの頻度ではないけど発生すること」や、「このケースの時は念のために書いておく注意事項」などは意外と多く生じています。
発生頻度が高い例は「ロット」です。全て同ロットにして欲しい場合や、ロットごとに段ボールを分けて出荷して欲しいなど、通常とは異なるリクエストが発生する際には「発注書の備考欄」に記載をして出荷担当者へ通知するルールを作っているケースがあります。
このような特殊ルールに対して、受注担当者からは、「〇〇さまの注文の〇〇の時は、ここにこう書いているんだけど、どうなるの?」という疑問が発生します。
この例の場合、「システムに専用備考欄があるから、そこに入力すれば出荷依頼データや帳票に反映されるよ」(システム導入担当者)。という回答と、実際の画面操作・帳票の確認をすることで、受注担当者の疑問を解消することができるでしょう。
備考欄の活用で解決するケースの他にも、カスタマイズで操作画面に選択窓を作ってしまうパターンや、運用でカバーする方法など、選択肢は複数あることが多いです。まずは現場の特殊ルールを理解して実装できる範囲でシステムに組み入れ、運用ルールを最適化することで、業務全体の標準化につなげていくことも可能です。「特殊ルールへの対応」ではなく、いかに削減できるかの視点も大切です。
③「情報共有作業はどうなるのか?」(メールやエクセルシート)

メールで顧客から注文を受けたり、取引先への発注を行ったりしている場合、複数人でメールを受信して漏れを防いだり、誰かが休暇になった場合のリカバリーに備えたりしている場合があります。企業によって工夫はさまざまで、顧客ごとにメールアドレスを発行する、役割分担を縦や横割りで明確化させて責任をもって進行をするなど、その企業の受発注環境に沿った運用を現場が作り上げてきている印象があります。
受注担当者から、「A企業案件はこのメンバー、B企業はこのメンバーで業務分担をしてメーリングリストを作っているんだけど、システムにしたら情報共有はどうなるの?」という疑問がありました。
この疑問への回答は、「情報共有はシステム内で行えるのと、メール通知を行うメンバーを登録することも可能ですよ」(システム導入担当者)。となります。
複数の企業から自社製品を受注している場合でも、TS-BASE 受発注内では注文情報が整理され、企業ごとや注文日ごとに閲覧することが可能です。各注文の進行状況も可視化されるため、システムにログインできれば、誰でもいつでも同じ情報を確認することができます。アナログ運用の時より、確実に情報共有のハードルは低くなるでしょう。
今まで同様のメンバーで業務を継続することも可能ですが、大体の企業はシステム導入をきっかけに、運用変更やメンバー編成を行うケースが多いです。現場担当者の意見を聞きながら、導入システムの特性を生かした新運用を築きあげていくことが大切です。
システムの種類は問わず、大切なのは現場メンバーをしっかり巻き込むこと
TS-BASE 受発注には「無料トライアル」のサービスもあります。導入に向けたフェーズによっては、カスタイマイズしたシステムのデモンストレーション環境を用意することも可能でしょう。受発注システム以外でも、各ベンダーで最適な体験を用意しているはずなので、問い合わせてみることをおすすめします。
▼TS-BASE 受発注のトライアルはこちら
システム導入で失敗している企業でありがちなのが、「現場に導入してみたら使えなかった」という事象です。導入に向けた動きも「現場始動」の場合もあれば「企業側始動」の場合もあります。後者の場合、会社的な方針で動くので、システム導入担当者も上への説得に重きを置いてしまい、現場は取り残されている場合もあります。
システムの導入は、日々の業務を効率化していくものです。実務を行う現場メンバーありきで推進することで、プロジェクトを成功に導くことができます。そのためにも、ベンダーの力も借りながら、現場メンバーの疑問に一つ一つ丁寧に答えていくことが大切です。