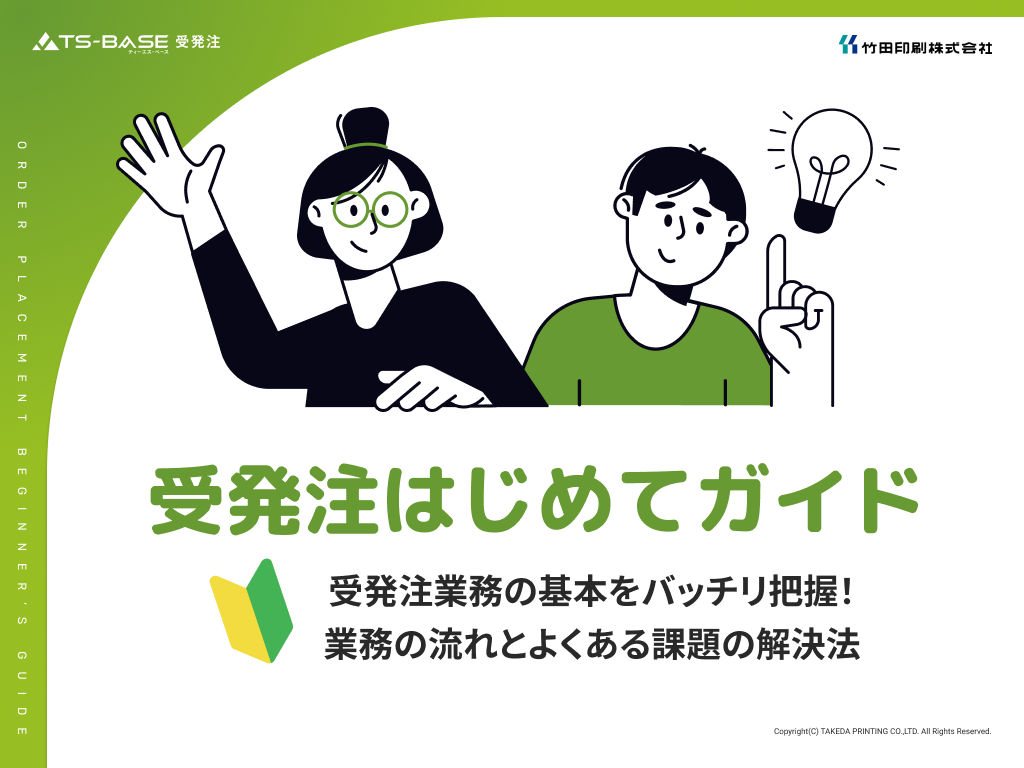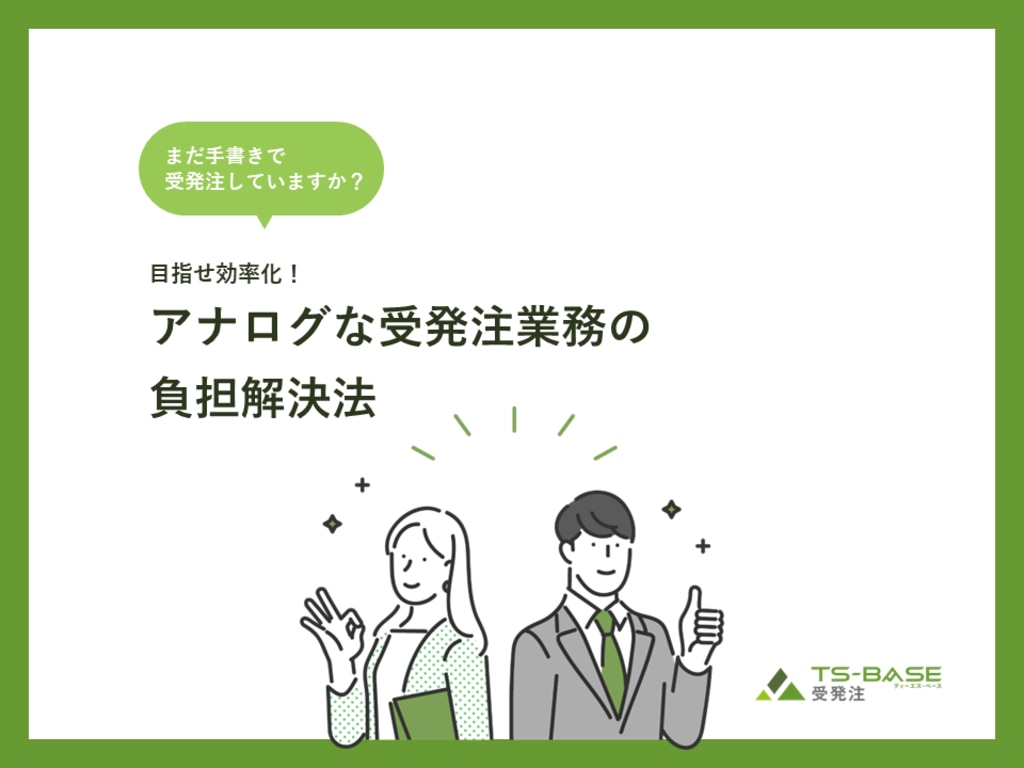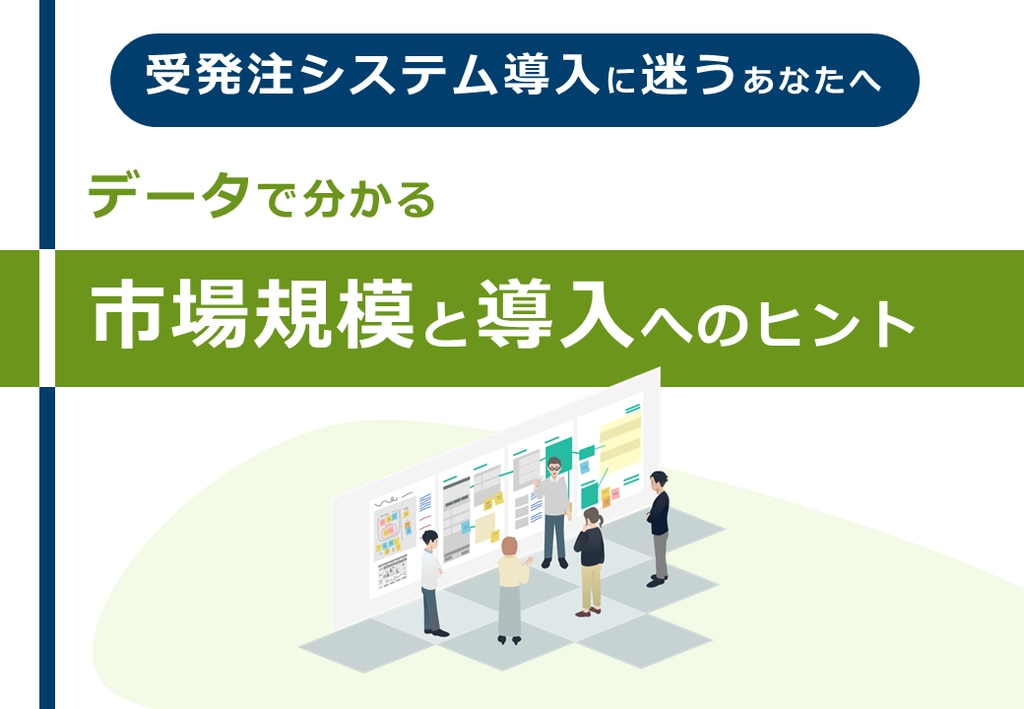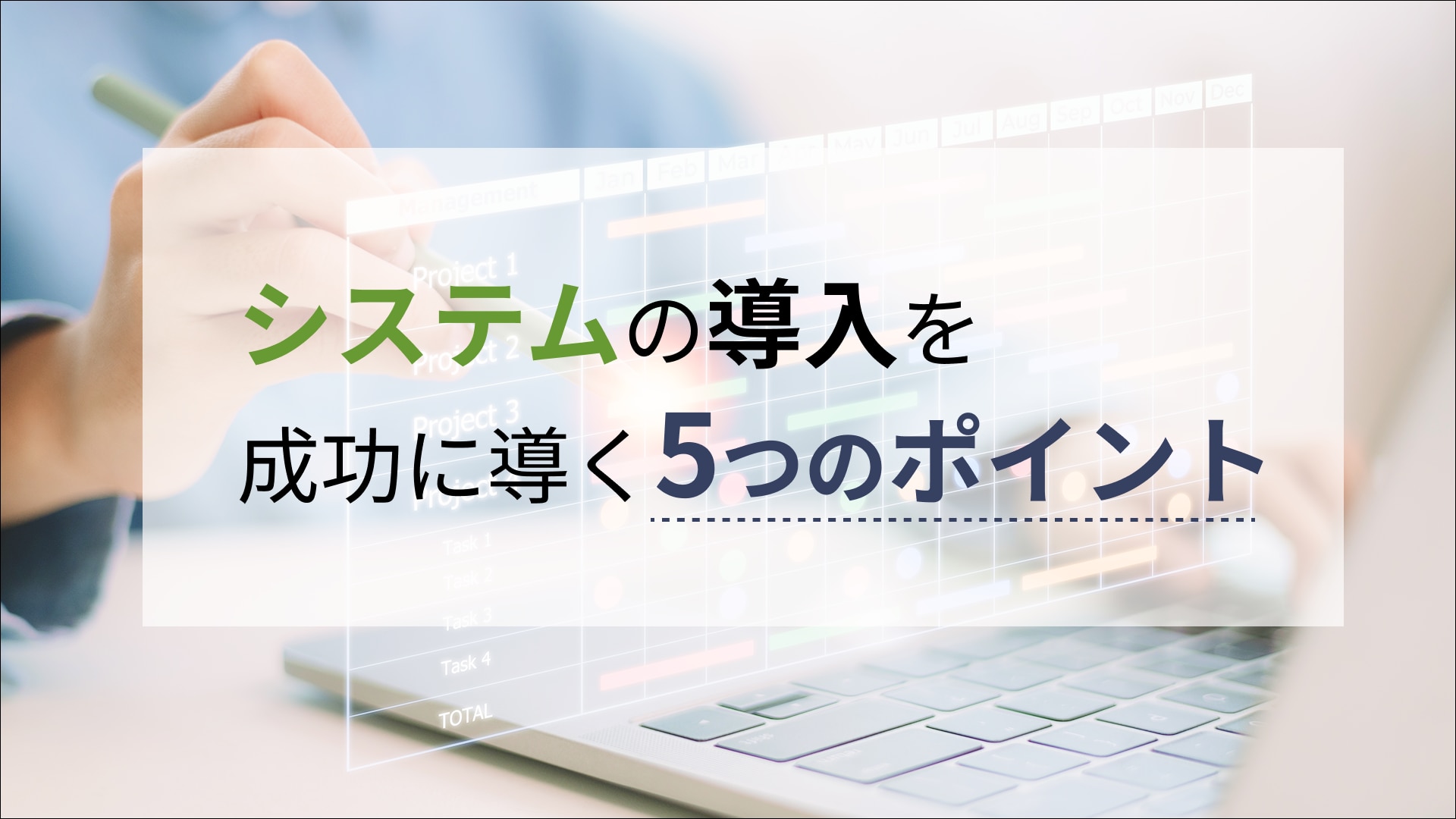
システムの導入を成功に導く5つのポイント
システム導入を成功させるには、どのような考えかたがあるのか。受発注管理システムを例に、5つの考えかたをご紹介します。システムの導入は手探りで進む場合も多く、障壁に悩まされる中、いつの間にか「システム導入がゴール」になっているケースが散見されます。当初の目的を達成し、導入したシステムを最大限に活用していくためにも、システムの選定は非常に大切です。受発注システムTS-BASE 受発注を提供する弊社が、お客さまとの商談の経験やベンダー目線をふまえ、選定時に必要なポイントをお伝えしていきます。
▽自社に合った受発注システムを選ぶコツが知りたい方は、こちらもご覧ください。
自社にとって最適な受発注システムを選定する7つの手順
目次[非表示]
「システムは全てを解決する」という間違い

「システムが全ての業務を自動で片付けてくれる」
受発注システムを含めた業務用システムの導入にあたって、このような考えをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか?テクノロジーの発展により、遠くない未来に実現する可能性はあるかもしれませんが、現時点で受発注管理システムが果たす役割は、残念ながらその域に達していません。
世の中に流通する受発注システムが果たす役割は、
「蓄積データを活用して一部業務を自動化することで、業務を効率化する」
ことです。
求める目的に対して合致するシステムを導入することができれば、現状をより良くすることは可能です。完全自動化は難しくても、システムを取り入れた運用で人が行っていた作業の〇割が削減されるというイメージで、人員削減の実現性は高いでしょう(業務内容やシステムの活用方法により異なります)。
世の中の「DX化しよう!」という流れや、さまざまなテクノロジーに関する情報の影響で、「システム化」というイメージが一人一人異なっている傾向があります。もし自社にシステムを導入しようと検討する場合、まずは導入しようとしているシステムは、一般的にどのような役割を果たしているのかを把握し、正しい期待値を持つようにしてみてください。
そして、システム導入を計画するということは、何らかの課題があるのではないでしょうか。「不便や辛さを解消したい」「業務環境を良くしたい」「人手不足に備えたい」などの目的があると思います。システムを導入することで、「実現したいこと」や「職場をこうしたい」という思いはとても大切です。それらから、最終的にどう在りたいかのゴールを設定することで、導入検討に向けた「ブレない軸」を作ることが可能になります。
システム導入はゴールではない

自社の業務にシステムを導入することは「ゴールではない」ことを念頭に置いてください。
弊社では「導入したシステムで業務が回らないので、リプレイスを考えている」という相談を受けたことが数回あります。これらは共通して、システムの導入が目的化してしまい、導入後の活用方法が定まっていなかったことが原因でした。
本来の目的とは異なるゴール設定で進んでしまった場合、時間やコストをかけた結果が元も子もない状況に陥ってしまいます。では、なぜシステムの導入を考えることになったのか。それは、前項で記載した通り、「実現したいこと」や「職場をこうしたい」という思いがあるからだと思います。
それらの「目的(以下、ゴール)」を達成するための手段として、システムを導入するという一つの「手段」があるわけです。この、「ゴール」と「手段」を自社の状況に合わせて正しく理解をすることで、導入検討だけではなく導入後の障壁も最小限に抑えることが可能になるでしょう。
システムの導入はゴールではなく、「受発注業務を行う現場の課題を解決し、業務環境をより良いものにするための手段」です。これをもとに、次項より導入をスムーズに進めるための考えかたを解説いたします。
受発注システム導入を成功に導く5つのポイント
受発注システムをはじめとするシステム導入は、多くのリソースを注いで推進するプロジェクトです。しかし、数多く経験することではないため、企業内にナレッジがなく、担当する人物の手腕に依存するケースが見受けられます。かけた労力に伴う良質な効果を得るためには、先述したゴールに沿ってブレない軸をつくることが大切です。今までお会いした企業担当者、及びベンダー側の視点から、推奨するポイントを5つご紹介します。
ポイント➀目的をスローガン化する

ゴールとなる目的を言葉にしてブレない軸をつくると、取捨選択や情報を整理する際に便利です。
システム導入に向けた商談や内部の検討が深まっていくと、新たに得る情報も増えるので「アレもできたら」「どうせならコレも」というように、やりたいことが過剰に膨らんでいく傾向があります。その時の気分や感情で判断をしていくと、導入した後に、「便利になったはずなのに、楽になった体感は全くない」というような本末転倒を招く恐れが高まります。これを回避するために、悩んだ時に立ち返るスローガンの設定は有効です。
システム導入からは外れますが、有名な監督が率いる「青山学院大学駅伝部」の、ある年のチームスローガンは、「大手町で笑おう」でした。大手町は、新春恒例の東京箱根間往復大学駅伝競走(通称、箱根駅伝)のスタートとゴールがある場所です。短くも印象的なこのスローガンは、「チームの最終目的が何で、どう在りたいのか」が分かりやすく言語化されている例になります。
スローガンは、「シンプルで関係者が分かりやすい言葉」を意識して考えてみてください。
【例】
- 部署の残業を〇割減らす
- FAXと関連する手入力作業を自動化
- 受発注業務の紙ゼロ大作戦
社風や担当者のキャラクターで個性を出してみると、インパクトがある分かりやすいスローガンになるかもしれません。スローガンは、ゴールとなる目的を関係者に浸透しやすくする効果もあるので、システムの導入完了までさまざまな役割を果たしてくれます。
ポイント②プロジェクトチームを編成する
システムの導入には、実際の業務を行う人との連携は欠かせません。プロジェクトの方向性を決めるスローガンが完成したら、チームを編成していきます。この際に注意したいことは、「スローガンを達成するためのキーパーソンを全員巻き込む」ことです。
推進方法の一つをご紹介します。
まず、起点となる作業を行う人へ最初に声掛けを行います。システム導入のプロジェクト開始の旨を説明し協力依頼を行います。この際、スローガンも伝えることで、同じ方向を向いて推進しやすくなるでしょう。そして、業務の流れや悩みなどを聞きつつ、その人と日頃連携しているチームや人物を紹介してもらい、同じようにヒアリングをしていきます。
この行為を繰り返し行い、スローガンを達成するための道筋を確認しながら、各工程のキーパーソンを数珠のようにつないで協力を仰いでいきます。同時に、現在の運用方法や課題を記録しながら、スローガンに関わる業務全体を俯瞰して把握をするよう努めましょう。
関係者の巻き込み漏れは、さまざまなやり直しや、「聞いていない!」というような感情のもつれなどにもつながり、プロジェクトの足枷になるので丁寧に行っていきましょう。可能であれば、稟議を書く人や決裁者にも状況を説明し、必要情報やタイミングなどを聞いておくと、後々協力を得やすくなる可能性があります。
ポイント③運用のシミュレーションを行う

候補のサービスやベンダーとの商談を進める際、「スローガンを常に念頭に置く」ことを意識して進行し、達成できそうなシステムがあったら、実際に業務の取り回しが可能なのか「シミュレーション」を行ってみてください。
スローガンを達成すると、「一連の業務を今より効率的に完遂できる状態」になります。注文から出荷依頼までの業務にシステムを導入するとしたら、物流倉庫へ出荷依頼を行って正しく発送されるまでが一連の業務です。
商談相手のベンダーと、システムを取り入れた新たな業務フローを作り上げていきましょう。その後、可能であれば、プロジェクトチームの各担当者へ協力を求め、実際のシステムを操作する無料トライアルを活用して業務シミュレーションを行うと現実的になります。
このタイミングで注意して欲しいのは、冒頭に述べた「システムは全てを解決するわけではない」という現実です。現状の業務をすべて自動化してくれる「100点満点のシステム」はなかなか見つかりません。
たとえ、機能がない場合でも、システム内の仕組みを組合せたり、人的運用を変えたりすることで達成できる場合もあります。「該当機能がないからダメだ」と、結果を焦ることなく、必ずベンダー側に実現方法を提案してもらうよう働きかけましょう。
シミュレーションの役割は、理想とするスローガンと現実をすり合わせしながら、実現の可能性を見出していくことでもあります。不可能を可能にする手段を探す根気強さもシステム導入には大切な要素になります。
ポイント④定量・定性両面からメリットを算出する
数字で表すことができる「定量」。数字で表すことができない「定性」の両面から、システムの導入後にどのようなメリットを得ることが出来るのかを算出してみましょう。これを行うことにより、目指すゴールの達成見込みや、導入によって削減できるリソースが可視化されるため、稟議を書く人や決裁者への説得力が増す情報にもなります。
定量面では、システム導入に対する費用対効果の算出をオススメします。「対応件数」「対応時間(分)」「人件費(時給)」などの情報から、基準となる「現在の運用費用対効果」を算出してみてください。
この作業から、「取引先の約4割にシステムを活用してもらって、100明細くらい受注をすればペイできる」というような、まず達成すべき目標も見えてくるでしょう。
費用対効果の算出方法は以下を参考にしてみてください。
定性面では、現場メンバーから聴取した「環境や感情面の課題」を、システム導入で解決が見込めるかに着目をしてみてください。例えばポイント②で、「取引先が使ってくれるのか不安」という内容を営業メンバーから聴取していたとします。そこに③で明確にしたシステムを導入した場合、その不安は解消されるのか、より良くするにはどうしたら良いのかを営業メンバーに聞いてみるとよいでしょう。
できれば、営業メンバーとシステムに抵抗がない取引先さまに「ポイント③の運用シミュレーション」へ参加してもらい、実際の業務さながらの作業をした感想を聞くことができれば、ただの憶測より説得力が増します。働きやすさは、モチベーションやパフォーマンスに直結します。システムの導入は、気持ちよく働くことができる環境づくりにも効果を発揮するので、定性面の評価も大きなメリットになると言えます。
ポイント⑤システム導入後の目標を設定する

「システム導入後」に目指す目標地点の設定は非常に大切です。導入前に必ず決定しておきましょう。
ポイント④で算出した費用対効果面の目標達成はまず目指したい指標だと思います。この目標を達成するために、受発注業務の現場担当者はもちろん、活用推進を先導する営業担当者や、テスト導入の協力を仰ぐ取引先など、推進するために必要な項目や担当者を確定しておき、目標到達までのロードマップを描いておきましょう。プロジェクトに参加したキーパーソンは目標を各チームに持ち帰り、メンバーに共有をしていくことで、業務に携わる全メンバーで活用を推進していくことが可能です。
ポイント➀で設定したスローガンを達成する運用の確立も大切です。現場業務のほか、システムで扱う商品数など導入範囲の拡大も計画的に行えると、今までシミュレーションしてきたことが絵に描いた餅にならず実現性が高まります。
ここで思いかえして欲しいのは、「システム導入はゴールではない」ということ。導入推進担当者やプロジェクトチームメンバーにとって、システム導入後は次なるステージの始まりになります。スローガンの達成、そして更なるメリットの創出のために、常に振り返りと修正を繰り返していく心づもりで向き合っていきましょう。
スムーズに推進する担当者の実例から考える、留意しておきたい点
弊社は受発注システム「TS-BASE 受発注」を提供する中で、多くの企業担当者さまとお会いしていますが、成約の有無は関係なく、スムーズに話が進む人は必ずしも受発注現場の担当者とは限りません。
一見すると「現場を知り尽くしている人が適任では?」と思いがちですが、先述してきた通り、受発注業務は複数部署の連携によって成り立ちます。全体の底上げが必要で、包括的な視点を持てる人が適任になるので、「現場の人だから良い」とはならないのです。
そして、連携部署との対話を大切にしている担当者が多いです。各部署のキーパーソンを巻き込み、スローガンを上手に活用してプロジェクトへの理解を促します。各部署の課題や悩みは丁寧にヒアリングして情報をまとめながら、現運用や状況の把握に努めています。
システム導入の担当者は、ベンダーと現場との橋渡し役です。現場の声をベンダーに届け、出来る限りシステムの力で解決していくこと。技術的に難しいものは、ベンダー・現場・担当者の全員が協力して解決策を導き出せるよう、バランスを取る役目が多くなります。
これから担当者を選任する場合、このような適正がある人を選ぶことがベストですが、この記事を読んでいる人の中には、「有無を言わさず任命された…」と、窮地に陥っている人もいるかもしれません。その場合は、まずはポイント②を意識してみてください。キーパーソンに事情を説明して情報を得ていくことに注力することで、自ずと改善すべきことは見えてくるはずです。その後、ポイント➀に戻り、協力者とともにスローガン作りをしてみても良いでしょう。
なぜシステムが必要なのかというと、「自社の受発注業務を効率化するため」になります。その目的を達成するために、会社は資金を投じて導入をするわけです。現在の状況と何を改善したいのかが分かれば、ベンダー側も対策を提示してくれます。関係各所を頼りつつ、迷いが生じたら目的に立ち返り、現場を第一に考えて推進することをおすすめします。