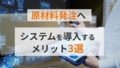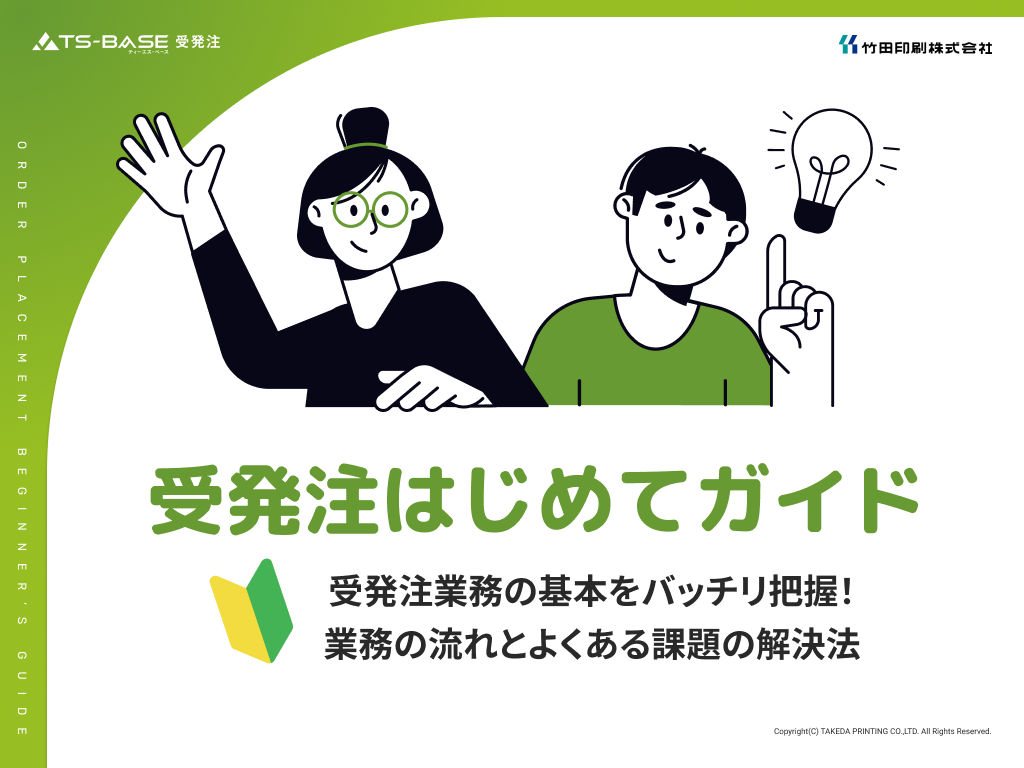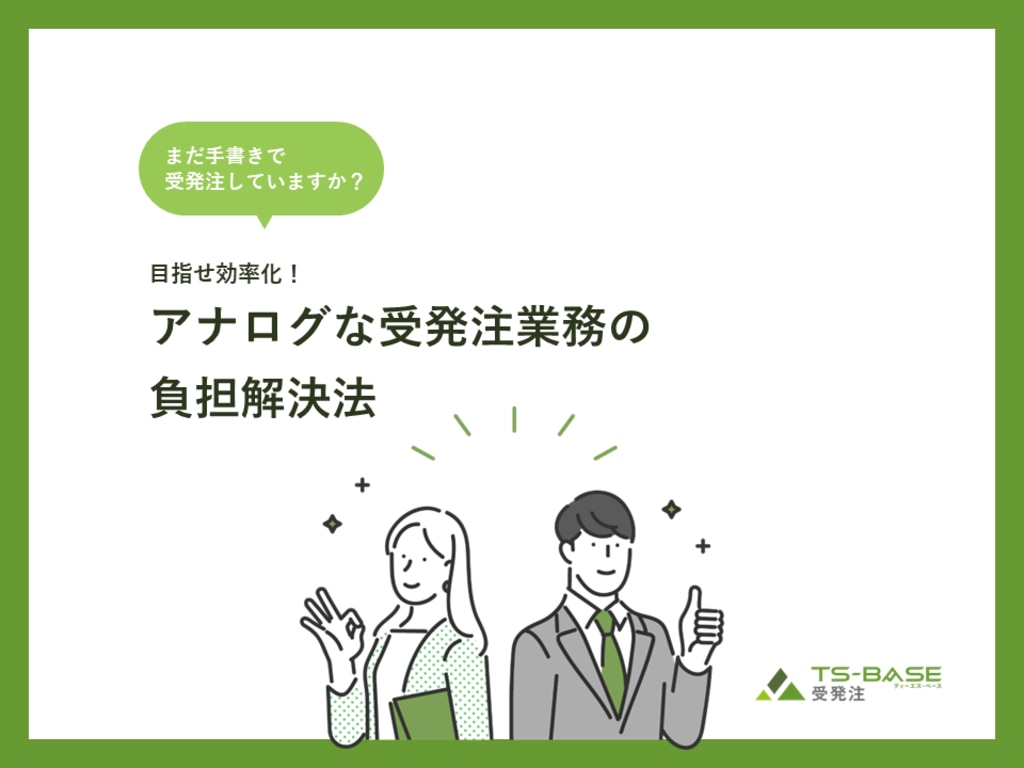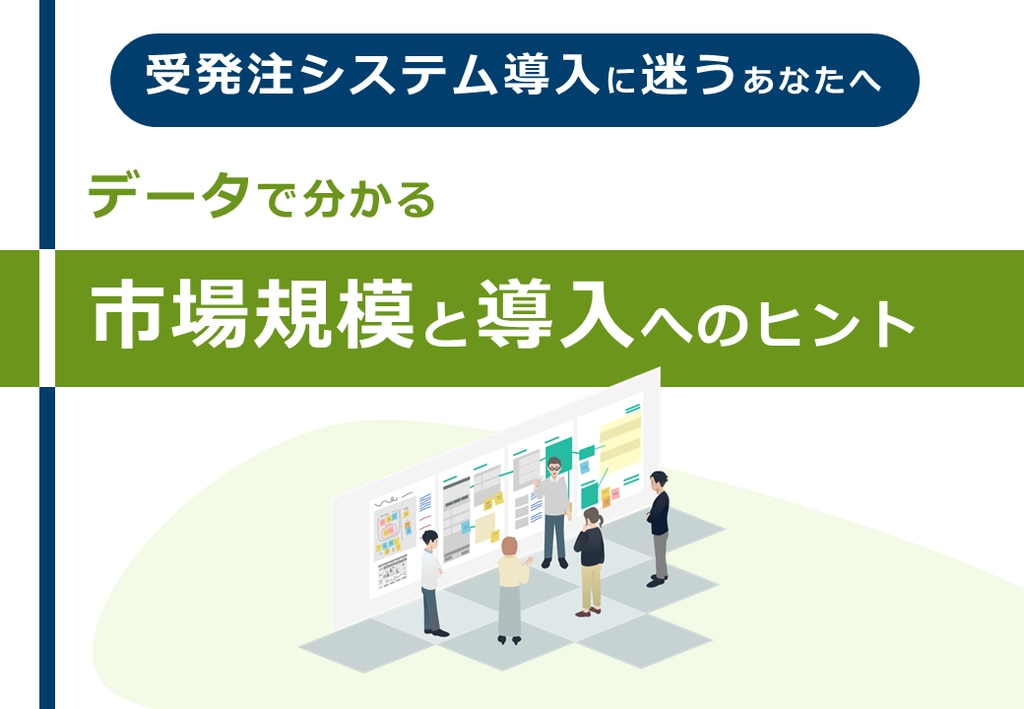資材管理とは?製造業における重要性と発注業務を効率化する方法を解説
製造業の安定した生産活動に欠かせない「資材管理」。言葉は知っていても、「具体的に何をすればいいのかわからない」「日々の業務に追われて、つい後回しになってしまう」という方も多いのではないでしょうか。
適切な資材管理は、欠品による生産停止や、過剰在庫によるキャッシュフローの悪化を防ぐ、いわば企業の生命線です。特に、現場からの資材の発注依頼がアナログな方法で行われていると、発注ミスや情報共有の遅れといった問題が発生しやすくなります。
本記事では、製造業における資材管理の重要性から、多くの企業が抱える共通の課題、そして明日から実践できる具体的な改善策までをわかりやすく解説します。さらに、これらの課題を根本から解決する「受発注システム」の活用法についてもご紹介します。
自社の資材管理と発注業務を見直し、生産性を向上させるための第一歩を踏み出しましょう。
目次[非表示]
- 1.製造業における資材管理とは?その重要性と目的
- 2.わかっていても難しい…製造業の資材管理でよくある3つの課題
- 3.資材管理を改善し、発注業務を効率化する5つの方法
- 3.1.方法1:資材管理のルールを策定し、関係者で共有する
- 3.2.方法2:エクセル台帳で資材と発注点を「見える化」する
- 3.3.方法3:5Sを徹底し、資材の保管場所を最適化する
- 3.4.方法4:定期的な棚卸で、実在庫の数量を正確に把握する
- 3.5.方法5:受発注システムを導入し、根本的な課題を解決する
- 4.受発注システムが、資材発注の課題を解決できる4つの理由
- 4.1.理由1:現場は「注文サイト」から頼むだけ。発注ミスがなくなるから
- 4.2.理由2:現場からの依頼を「見える化」。発注状況をリアルタイムに共有できるから
- 4.3.理由3:発注依頼の集計・転記がゼロに。購買担当者の負担を大幅に軽減できるから
- 4.4.理由4:紙と電話でのやり取りが激減。部門間の連携がスムーズになるから
- 5.失敗しない!自社に合った資材管理・受発注システムの選び方
- 6.TS-BASE 受発注で資材管理・発注業務の効率化を実現しよう
製造業における資材管理とは?その重要性と目的
製造業における資材管理とは、製品の生産に必要な「資材」を、適切な「量」、適切な「タイミング」、適切な「場所」に供給できるよう、管理・維持する活動全般を指します。
ここでの「資材」とは、製品の元となる原材料や部品だけでなく、製造過程で使用する工具、機械のメンテナンス部品、梱包材、さらには事務用品といった副資材まで、事業活動で必要となるあらゆる物品が含まれます。
資材管理が適切に行われていないと、「必要な時に資材がない(欠品)」、あるいは「不要な資材が多すぎる(過剰在庫)」といった事態を招き、企業の経営に直接的なダメージを与えかねません。
資材管理の主な目的は、以下の3つです。
- 生産活動の安定化:欠品を防ぎ、生産ラインを止めることなく、計画通りに製品を製造できるようにします。
- コストの最適化:過剰在庫をなくし、保管コストや管理コストを削減します。また、適切なタイミングで発注することで、不要な緊急手配によるコスト増を防ぎます。
- キャッシュフローの改善:在庫は、会計上は「資産」ですが、現金化されるまでは企業の資金を圧迫します。在庫を適正な水準に保つことで、企業の資金繰りを健全化します。
安定した企業経営の土台を築く上で、資材管理は極めて重要な役割を担っているのです。
わかっていても難しい…製造業の資材管理でよくある3つの課題
資材管理の重要性は理解していても、日々の業務の中で完璧に実践するのは難しいものです。特に、昔ながらの方法で管理している現場では、多くの企業が共通の課題を抱えています。
ここでは、製造業の資材管理でよくある3つの課題について、具体的なシーンを交えながら解説します。自社の状況と照らし合わせながら、課題を明確にしていきましょう。
課題1:紙やエクセルでの管理による発注・転記ミス
多くの現場で今なお行われている、紙の管理簿やエクセルを使った資材管理。手軽に始められる反面、人的なミスが起こりやすいという大きな課題を抱えています。
「品番の桁数が多くて、発注書に書き写すときに間違えてしまった」
「似たような名前の資材を、間違えて発注してしまった」
「エクセルファイルが担当者ごとに複数存在し、どれが最新の在庫情報かわからない」
このような経験はないでしょうか。
手作業による管理は、担当者のスキルやその日のコンディションによって、品質にばらつきが出てしまいます。特に、品番や数量の転記作業は単純なようでいて、集中力が必要です。こうした小さな入力ミスが、誤った発注につながり、結果として不要な在庫を抱えたり、必要な資材が届かなかったりといったトラブルを引き起こします。
また、特定の担当者しかわからない「属人化」したエクセル管理も問題です。その担当者が不在の際に誰も状況を把握できず、業務が滞ってしまうリスクも潜んでいます。
課題2:在庫差異による過剰在庫や欠品
「帳簿上は在庫があるはずなのに、倉庫を探しても見つからない…」これも、資材管理における典型的な課題です。データ上の在庫数と、実際の在庫数が合わない問題は、多くの現場担当者を悩ませています。
この在庫差異は、以下のような原因で発生します。
入庫・出庫時の記録漏れや入力ミス
急な出庫で、後で記録しようと思って忘れてしまう
返品や不良品の処理がデータに反映されていない
在庫数が正確に把握できていないと、適切な発注判断ができません。まだ在庫があると思って発注しなかった結果、いざ使おうとした時に欠品が発覚し、生産ラインを止めざるを得なかったり、もう無くなったと思って発注したら、倉庫の奥から在庫が見つかり、過剰在庫になってしまったりすることもあります。
欠品は機会損失に、過剰在庫は保管コストの増大やキャッシュフローの悪化に直結します。在庫差異は、経営に直接的なダメージを与える深刻な課題なのです。
在庫差異への対策は、こちらでも詳しく解説しています。
課題3:部門間の情報共有不足によるタイムラグ
資材管理は、製造部門だけでなく、営業、購買、経理など、さまざまな部門と連携して行われます。しかし、部門間の情報共有がスムーズに行われていないことで、生産効率の低下を招いているケースが少なくありません。
例えば、営業部門が急な大口案件を受注したとしても、その情報がリアルタイムに購買部門や製造部門に共有されなければ、資材の調達が間に合わないという事態が発生します。生産計画の見直しや急な発注が必要となり、現場の混乱を招く原因となります。
また、製造現場で特定の資材の消費ペースが想定を上回った場合でも、その情報が実際に資材の発注を行う購買部門に迅速に伝わらなければ、在庫が枯渇するまで誰も気づかない、ということも起こり得ます。
このように、部門ごとに情報が分断され、伝達にタイムラグが生じると、対応が後手に回ってしまいます。その結果、特急料金で資材を調達して余計なコストが発生したり、最悪の場合、納期遅延によって顧客の信頼を失ったりすることにもなりかねません。
資材管理を改善し、発注業務を効率化する5つの方法

資材管理の課題を解決し、日々の発注業務を効率化するためには、何から手をつければよいのでしょうか。ここでは、すぐに取り組める改善策から、根本的な課題解決につながる方法まで、5つの具体的なアプローチを紹介します。
方法1:資材管理のルールを策定し、関係者で共有する
最初のステップは、資材管理に関する社内ルールを明確に定めることです。ルールがあいまいなままでは、担当者によってやり方が異なり、ミスや混乱の原因となります。
まずは、以下のような基本的な項目についてルールを決め、関係者全員で共有しましょう。
記録のルール:
いつ(入庫時、出庫時など)
誰が(現場担当者、管理部門など)
何を(品番、数量、日付など)
どこに(管理台帳、日報など)記録するのか
発注のルール:
誰が発注の判断をするのか
発注点をいくつに設定するのか
発注時の承認フローはどうするのか
保管のルール:
資材はどこに保管するのか(ロケーション管理)
資材の置き場所を示すラベルや表示のルール
このように、業務の基準を統一することで、「あの人にしかわからない」といった属人化を防ぎ、誰もが同じ品質で作業できるようになります。これが、資材管理を改善する全ての土台となります。
方法2:エクセル台帳で資材と発注点を「見える化」する
ルールが決まったら、次はエクセルなどを使って資材の情報を「見える化」しましょう。紙の伝票や個人の記憶に頼るのではなく、一覧性のあるデータとして管理することが重要です。
資材管理台帳には、最低でも以下の項目を盛り込みましょう。
資材名、品番、型番
保管場所(ロケーション)
現在の在庫数
安全在庫数(最低限、保持しておくべき在庫量)
発注点(この在庫数を下回ったら発注する、という基準)
エクセルの関数を活用すれば、在庫数が発注点を下回った際にセルを色付けするなど、発注タイミングを視覚的に知らせる工夫も可能です。
ただし、エクセル管理は手入力が基本となるため、入力ミスや更新漏れ、ファイルの属人化といった課題が残る点には注意が必要です。
方法3:5Sを徹底し、資材の保管場所を最適化する
データ上の管理と並行して、物理的な保管環境を整えることも欠かせません。そのために有効なのが、「5S」の徹底です。5Sとは、「整理・整頓・清掃・清潔・躾」の頭文字をとったもので、職場環境を維持・改善するためのスローガンです。
整理 | 不要な資材を処分し、必要なものだけを置く。 |
整頓 | 資材の置き場所を決め、誰が見てもわかるように表示する(ロケーション管理)。 |
清掃 | 倉庫や棚をきれいに保ち、資材の品質劣化を防ぐ。 |
清潔 | 整理・整頓・清掃の状態を維持する。 |
躾 | 上記4つのルールを守る習慣を全員で身につける。 |
倉庫内が整理整頓されていれば、資材を探す時間が短縮されるだけでなく、在庫数を正確に把握しやすくなります。「どこに何がいくつあるか」が一目瞭然の状態を作ることが、管理精度向上の鍵です。
方法4:定期的な棚卸で、実在庫の数量を正確に把握する
どれだけ気をつけていても、日々の入出庫の中でデータと実際の在庫数にズレが生じてしまうことはあります。そのズレを修正し、在庫の正確性を保つために不可欠なのが「棚卸」です。
「月末」「四半期末」など、定期的にタイミングを決めて、すべての資材を実際に数え、データ上の在庫数と照合します。
もし差異が見つかった場合は、その原因を必ず調査しましょう。「なぜズレが生じたのか」を突き止め、再発防止策を講じることが重要です。例えば、「記録漏れが多い」のであれば、記録方法やフローの見直しが必要です。
棚卸は手間のかかる作業ですが、これを定期的に行うことで在庫データの信頼性が格段に向上し、適正な発注判断につながります。
方法5:受発注システムを導入し、根本的な課題を解決する
これまで紹介した4つの方法は、資材管理を改善する上で非常に有効です。しかし、これらはあくまでも運用上の工夫であり、人的ミスや情報共有のタイムラグといった、アナログ管理に起因する根本的な課題を完全になくすことは困難です。
そこで、より抜本的な解決策として有効なのが、「受発注システム」の導入です。
受発注システムを導入すれば、これまで手作業で行っていた発注業務や在庫管理をデジタル化し、大幅に効率化できます。現場からの発注データが一元管理されることで、転記ミスや記録漏れといったヒューマンエラーを防止。リアルタイムで正確な在庫数を把握できるため、欠品や過剰在庫のリスクも低減します。
次のセクションでは、受発注システムが具体的にどのようにこれらの課題を解決するのか、その理由を詳しく解説します。
受発注システムが、資材発注の課題を解決できる4つの理由

アナログな資材発注は、現場と購買部門の双方にとって、多くの手間とコミュニケーションコストを発生させます。
なぜ受発注システムを導入することで、これらの課題が解決に向かうのでしょうか。ここでは、現場と購買部門のコミュニケーションが劇的に改善される4つの理由を解説します。
理由1:現場は「注文サイト」から頼むだけ。発注ミスがなくなるから
受発注システムを導入すると、現場担当者はスマートフォンやPCの「注文サイト」から、必要な資材を選んで発注依頼をするだけになります。
これにより、現場担当者は品番や品名を、紙に手書きしたり内線電話で伝えたりする必要がなくなります。
注文サイトに表示される資材一覧から、必要なものを選んで数量を入力するだけなので、品番の聞き間違いや書き間違いといった、人的な発注ミスを根本からなくせます。
「よく頼む資材」をお気に入り登録したり、過去の注文履歴から再注文したりもできるため、発注依頼の手間が大幅に削減されます。
購買部門では、これまで電話、FAX、メール、口頭など、バラバラな方法で届いていた現場からの発注依頼が、システムの管理画面に正確なデータとして集約されます。
理由2:現場からの依頼を「見える化」。発注状況をリアルタイムに共有できるから
システムを導入することで、現場からの発注依頼の状況が、関係者全員に「見える化」されます。
現場担当者は、自分が依頼した資材が、今「購買部門で確認中なのか」「すでに発注済みなのか」といった進捗状況を、注文サイト上でいつでも確認できます。
これにより、購買部門への「あの件、どうなっていますか?」といった、進捗確認の電話やメールが不要になります。
購買部門では、どの現場から、いつ、何の発注依頼がきているのかを管理画面から一覧で把握できます。
対応状況(未対応、対応中、完了など)もシステム上で管理できるため、依頼の見落としや対応漏れを防ぎます。
理由3:発注依頼の集計・転記がゼロに。購買担当者の負担を大幅に軽減できるから
受発注システムは、これまで購買担当者が多くの時間を費やしてきた、現場からの注文の取りまとめや、仕入先への発注書作成といった業務を劇的に効率化します。
各現場から集まった複数の発注依頼を、システムが自動で取りまとめてくれるから、エクセルへの転記や手作業での集計はもう必要ありません。
集約されたデータをもとに、ボタン一つで仕入先への発注書を作成し、FAXやメールで自動送信できます。転記作業がなくなるため、仕入先への誤発注も防げます。
このような単純作業から解放されることで、購買担当者は、コスト削減のための価格交渉や、より良い条件の仕入先を探すといった、本来注力すべき付加価値の高い業務に時間を使えるようになります。
理由4:紙と電話でのやり取りが激減。部門間の連携がスムーズになるから
受発注システムは、これまで当たり前だった「紙の依頼書」と「電話での確認」によるコミュニケーションを、デジタルな情報共有へと変革します。
現場からの発注依頼から、購買部門での確認、仕入先への発注まで、すべてのやり取りの記録がシステム上に残ることで、口頭での「言った・聞いていない」といった水掛け論や、メモの紛失といったトラブルがなくなります。
さらに関係者全員が、システムを通じて常に同じ最新の情報を共有できるため、認識の齟齬が生まれにくくなります。
また、急な仕様変更や発注内容の確認も、システム上の正確な記録をもとに行えるため、迅速かつ確実な対応が可能です。
このように、情報伝達のスピードと正確性が向上することで、部門間の連携がスムーズになり、組織全体の生産性向上につながります。
失敗しない!自社に合った資材管理・受発注システムの選び方
受発注システムの導入は、資材管理と発注業務を劇的に改善する可能性を秘めています。しかし、自社に合わないシステムを選んでしまっては、期待した効果が得られないばかりか、現場の負担を増やしてしまうことにもなりかねません。
ここでは、数あるシステムの中から自社に最適なものを選ぶための、3つの重要なポイントを解説します。
ポイント1:自社の課題を解決できる機能が揃っているか
まず最も重要なのは、「システムを導入して、何を解決したいのか」を明確にすることです。多機能で高価なシステムが、必ずしも自社にとって最適とは限りません。
「現場からの発注依頼の取りまとめに時間がかかっている」という場合、複数の依頼を自動で集計する機能や、発注書を自動で作成・送信する機能は必須でしょう。
また、「電話やFAXでの聞き間違い・書き間違いによる発注ミスが多い」という課題には、現場担当者がカタログ形式で商品を選べる機能や、品番で検索できる機能が有効です。
「発注状況の問い合わせ対応に追われている」のようなケースでは、現場担当者が自分で発注状況のステータスを確認できる機能があると、購買部門の負担を軽減できます。
このように、自社の課題を洗い出し、それを解決するために「絶対に譲れない機能」と「あれば嬉しい機能」を整理することが、システム選びの第一歩です。課題解決に直結する機能を備えた、身の丈に合ったシステムを選びましょう。
ポイント2:現場の誰もが使いやすい操作性か
システムの導入を成功させる鍵は、実際にシステムを使う現場の担当者が、ストレスなく使いこなせることです。特に、ITツールに不慣れな従業員も多い製造業の現場では、操作のわかりやすさが極めて重要になります。
確認したいポイント:
マニュアルを熟読しなくても、直感的に操作できる画面か。
普段使っているスマートフォンやタブレットからでも、簡単に見やすく操作できるか。
文字の大きさやボタンの配置など、誰にとっても見やすいデザインか。
導入を決める前に、無料トライアルやデモンストレーションを活用し、必ず複数の現場担当者に実際に触ってもらいましょう。「これなら自分でも使えそう」という声が多くの人から上がることが、定着の目安となります。どんなに高機能でも、現場で使われなければ意味がありません。
▼受発注システム「TS-BASE 受発注」の無料トライアルはこちら
ポイント3:導入後の運用を見据えたサポート体制があるか
システムは、導入して終わりではありません。スムーズに運用を軌道に乗せ、継続的に活用していくためには、提供元のベンダーによるサポート体制が欠かせません。
初期設定やデータの登録、運用開始後のサポート体制や定着に向けた説明会の実施など、機能や価格だけで判断するのではなく、導入前から導入後まで、長期的に伴走してくれるパートナーとして信頼できるベンダーかどうかを見極めることが重要です。手厚いサポートがあれば、システム導入に関する担当者の不安を解消し、プロジェクトを成功に導いてくれるでしょう。
TS-BASE 受発注で資材管理・発注業務の効率化を実現しよう
ここまで、製造業における資材管理の重要性から、アナログな管理が抱える課題、そしてシステムによる解決策までを解説してきました。
「現場からの発注依頼の取りまとめが大変…」
「電話やFAXでの発注ミスをなくしたい…」
「部門間の情報共有をスムーズにして、生産性を上げたい…」
もし、このような課題を解決したいとお考えなら、「TS-BASE 受発注」の導入はいかがでしょうか。
TS-BASE 受発注は、製造業の現場における「資材・備品の発注」に関する課題解決に特化したクラウド型の受発注システムです。
現場担当者は、使い慣れたスマートフォンやPCから、まるでネットショッピングのように簡単な操作で資材の発注依頼ができます。一方、購買部門の担当者は、各所からバラバラに届いていた依頼をシステムの管理画面で一元的に受け取り、集計から仕入先への発注までを効率的に行うことが可能です。
TS-BASE 受発注は、ECサイトのような画面で簡単に操作できる特徴が、ご導入いただいた多くの方に支持されています。
さらに、豊富な機能の中から個々の業務フローに合った機能や設定をカスタマイズしてご提供します。
また、専任の担当者が1対1で導入から定着までサポートするから、システムの導入が初めてという方でも安心してお任せいただけます。
資材管理と発注業務の効率化は、企業の生産性を高め、競争力を強化するための重要な一歩です。
受発注システムの導入で、業務効率化と生産性向上を実現しませんか?