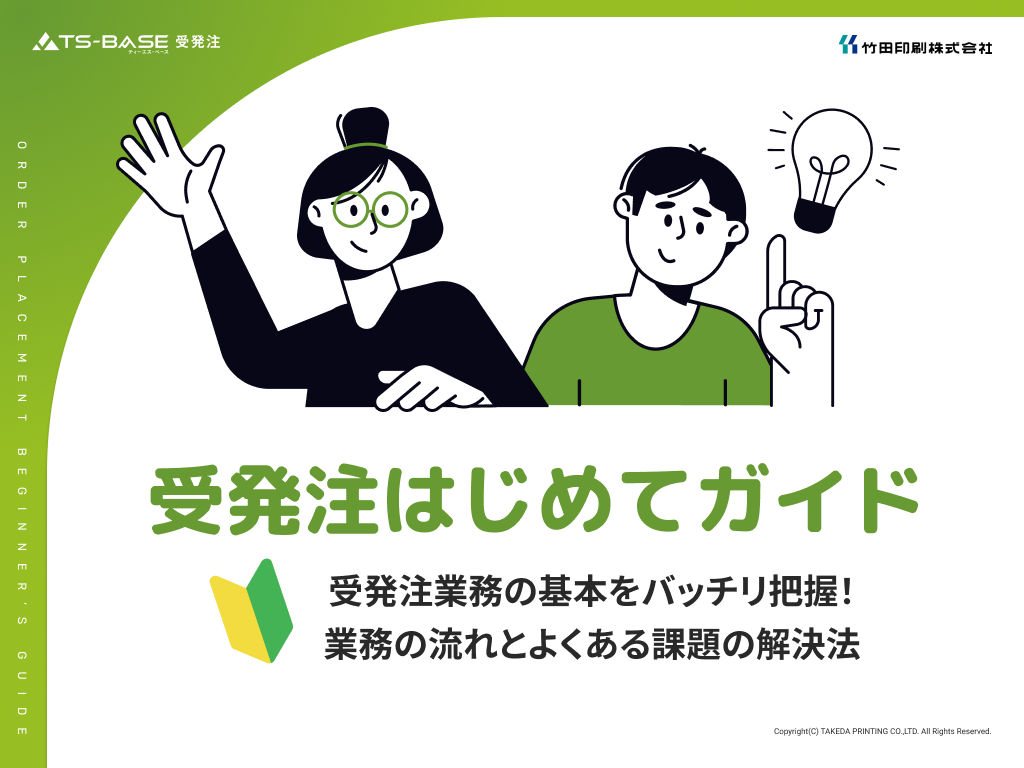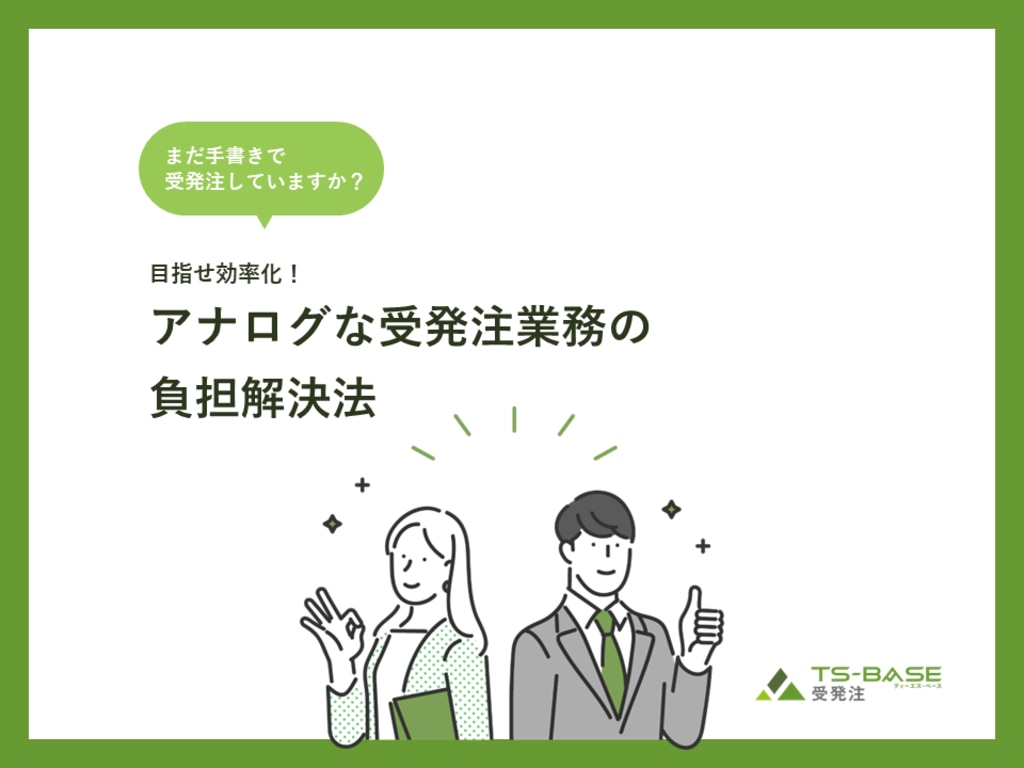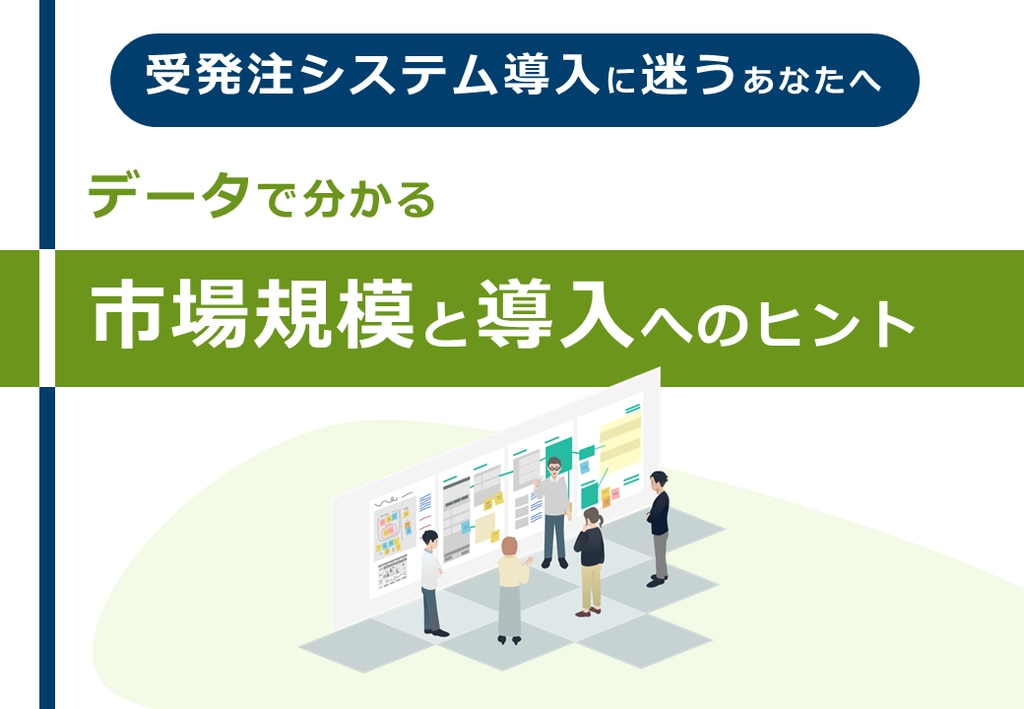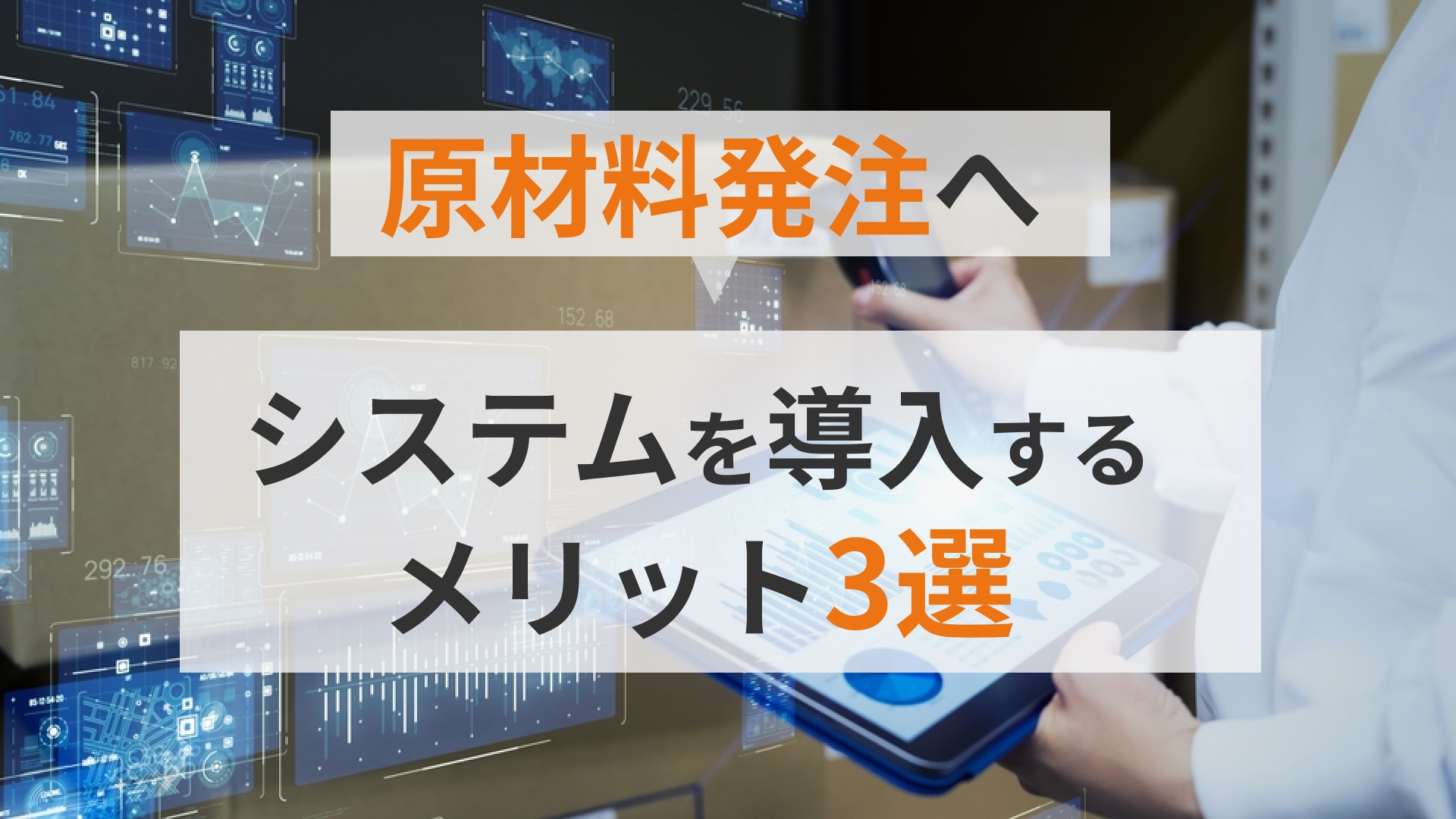
原材料発注へシステムを導入するメリット3選
製造業における原材料発注の課題解決には、関係各所のコミュニケーションを円滑にすることが有効です。原材料の定義はさまざまですが、製品が何であれ、「出荷する完成品を製造するために必要な材料」という意味で、欠かせない要素という点は共通です。原材料をとりまく課題は多くありますが、製造現場が担う「受注した製品を納期通りに出荷する」という本来の業務に集中できる環境づくりが何より優先すべきことだと言えます。「TS-BASE 受発注」という受発注管理システムを提供する竹田印刷が、製造業に携わる企業担当者から聞いた話をもとに、原材料に関わる課題と対策の一つ「システム導入のメリット」について解説します。
現場主導で円滑化を求められる「原材料」

「コスト削減要請が結構大変なんですよね」。
ある企業の生産管理部門のご担当者さまから、このような話を聞きました。企業が持つ経営資源をどのように分配するのかは経営方針によって異なりますが、とりわけ製造現場へ求める方針は厳しい内容が多い傾向であるため、現場責任者の悩みの種になりがちです。
製造現場における原材料発注および管理においても、「直接売上になるものではない」という理由で経営資源の投資対象として優先度は低く、どちらかというと現場主導で円滑な運用を求められている領域です。しかし、「受注した製品を納期通りに出荷する」という使命を担う製造現場にとって、必要材料の確保は本来の業務とは少し外れており、できれば労力をかけたくない部分でもあります。
また、原材料発注を生産管理部門が行っている場合、製造現場との物理的な距離感にもよりますが、「実際に現場にある原材料」「納期に対して必要となる原材料の実数」など、実際に現場にある原材料の在庫認識の齟齬、関連情報のコミュニケーション不足などは発生しがちな課題です。「追加注文を依頼したはずが一向に納品されない」「重複して納品された」なども含め、情報共有や伝達部分のエラーが円滑な運用の妨げになっているケースも多く、現場責任者のリソースが割かれる要因にもなっています。
コストカットは費用面だけではなく、さまざまなムダの削減も含まれます。その中で、安全かつ高品質なモノづくりも同時に求められるため、「何かを変えたいけど、何から手をつけていいのか…」と、思案する現場責任者のかたは多く存在しています。
サプライヤーからの調達をシステムの力で円滑化
原材料発注は、製造の根幹を支える大切な要素です。この部分が不安定だと、安定的な製品供給や企業全体の信用に関わる問題へ発展してしまいます。昨今、省人化への取り組みとして、さまざまな業務のテクノロジー化が進んでいますが、原材料調達業務においても、システムの導入で効率化を図る企業は年々増加しています。
システム化の根幹ともいえる「情報のデータ化・可視化」は、先述した「何かを変えたい…」という“全ての何か”に対する足がかりになっていくでしょう。実際にシステムを投入することで、どのようなメリットを得ることができるのか。代表的な例を3つご紹介します。
①コミュニケーションの円滑化

「発注までの時間が短縮できる」を筆頭に、さまざまな場面のコミュニケーションが円滑になるのがメリットです。
注文時も、写真を見ながら発注ができるように、いつでも場所を選ばずに注文ができるようになるので、FAXや注文書での注文より俄然便利になります。また、アナログでの受発注では、注文から到着まで1週間かかっていたものも、システムの活用で納期の短縮ができたり、今まで設定されていた注文締切日も廃止できたりなどのタイムロス対策に有効的です。
原材料の発注権限が「製造現場」「生産管理課などの他部署」どちらの場合でも、双方が見える化された同情報の確認が可能になると、コミュニケーションが図りやすくなります。過剰に残り続けている品番・減りが早い品番・注文回数が多い品番などの情報も明確化・共有できるようになるため、データの振り返りから「適正な在庫数」や「定期的な納入」などに対する意見交換もしやすくなるでしょう。
②誤発注防止

転記作業や手入力が要因の「誤発注」への対策ができます。
アナログでの業務では、注文者・受注担当者ともに人の手作業が多く発生しがちです。原材料は似たような品番で管理をしている場合が多く、英数字を1つ間違えただけで異なる商品が届いてしまいます。
このようなミスに対して、Web注文の導入が効果的です。通信販売サイトのような画面での注文は、対象部品の外観を確認しながら、サイズを選択するだけで注文が可能になります。原材料の在庫情報を連携しておけば、同画面に実在庫数も表示されます。複数の情報を1つの画面で確認をしながら注文ができるので、誤発注のリスクは各段に低くなるでしょう。
③管理業務の負担軽減

システム化は、さまざまな受注管理業務の効率化が見込めます。
よく耳にするのは、「注文者からの問い合わせの減少」です。要因は先述した①②と関わりが深く、システム化により、注文者自らが必要情報を確認しにいける環境が整えられることにあります。
導入前は、「この商品の在庫はある?」「これはどのメーカーに頼むの?」「これを〇日までに届けてもらえる?」などの「注文」や「納期」に関する問い合わせ対応に時間を割いていた企業も、問い合わせが圧倒的に少なくなったという声が複数挙がっています。
原材料調達の一気通貫を実現するTS-BASE 受発注
TS-BASE 受発注の強みの一つとして、「現場からの注文~サプライヤーへの発注を一気通貫できる運用の構築が可能」という点があります。
注文時の情報をデータ化することで、情報を活用して業務全体の効率化を目指すベースが作れます。こうすることで、システム内で複数部署間の情報のやり取り、コミュニケーションのルートを絶やさず、原材料調達先の各社へつなぐ運用が実現できるのです。注文情報の有効的な活用方法は、運用や扱うモノによって異なります。TS-BASE 受発注は、企業さまの現運用状況を確認後、それぞれの業務環境に沿ったシステムの活用方法のご提案・運用の確立をサポートいたします。
▽現場からの資材発注業務へTS-BASE 受発注を導入した事例
さまざまな機能を組み合わせて、貴社にとって最善な受発注業務環境をご提案させていただきます。原材料発注業務やサプライヤーからの調達業務に課題を抱えるご担当者さまは、ぜひ一度お問合せをお願いいたします。