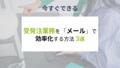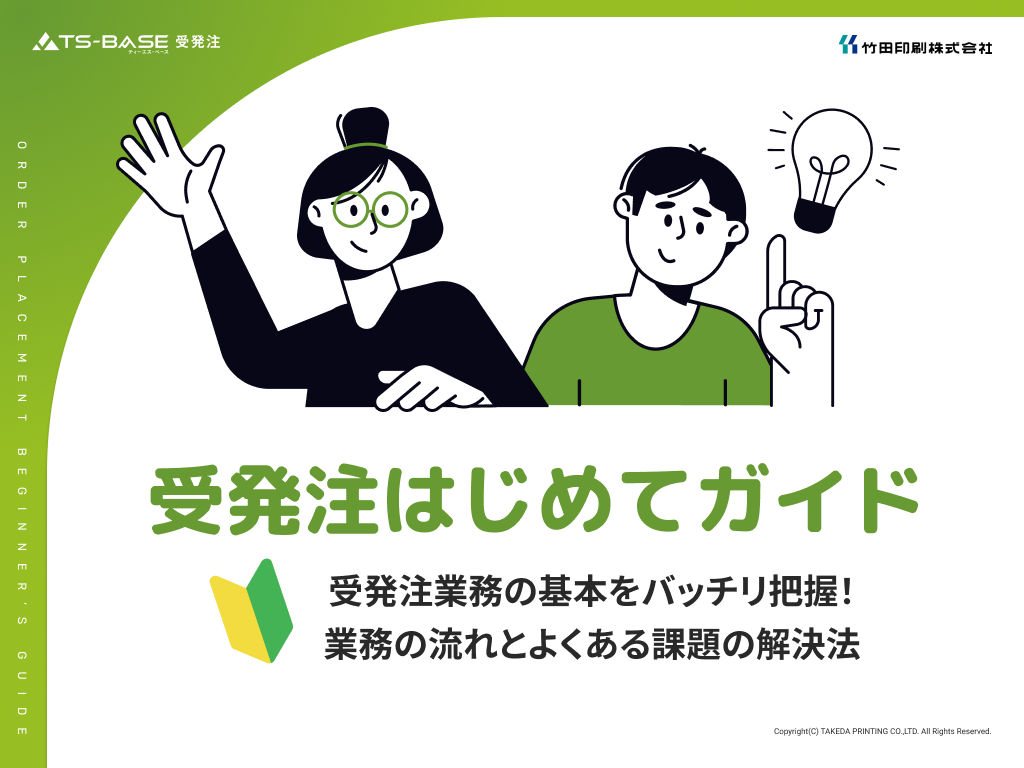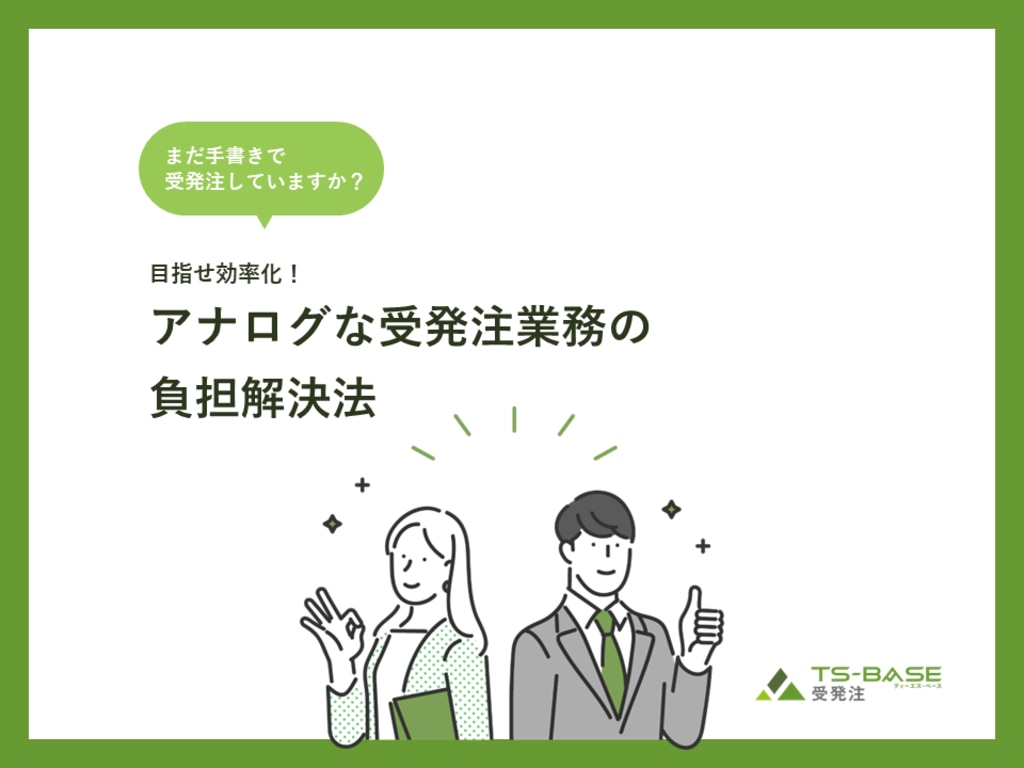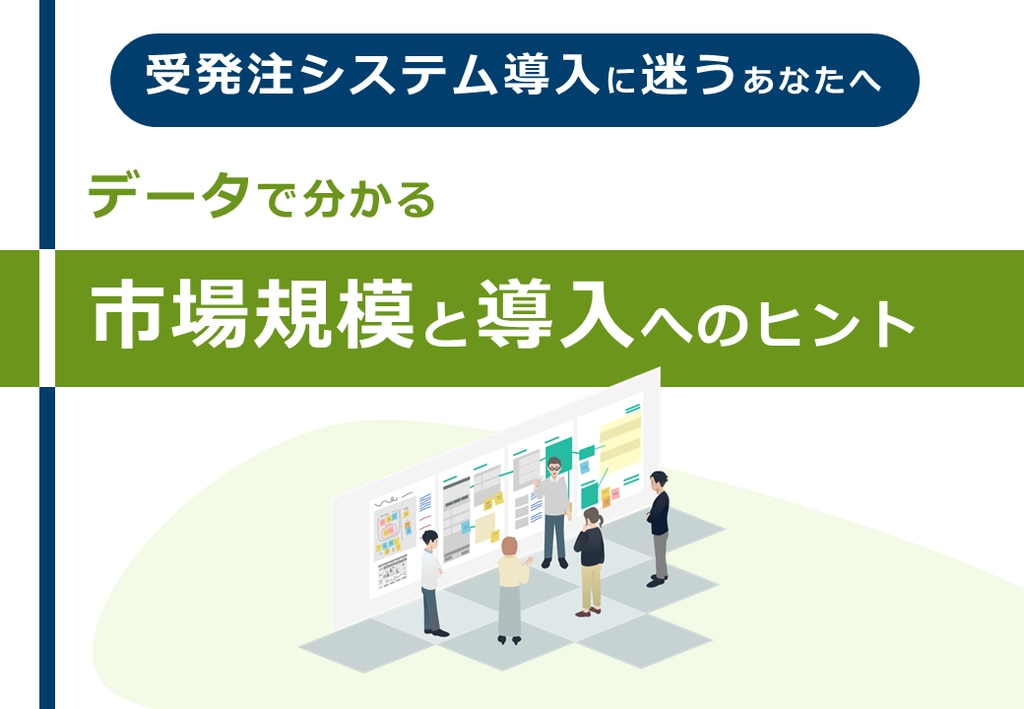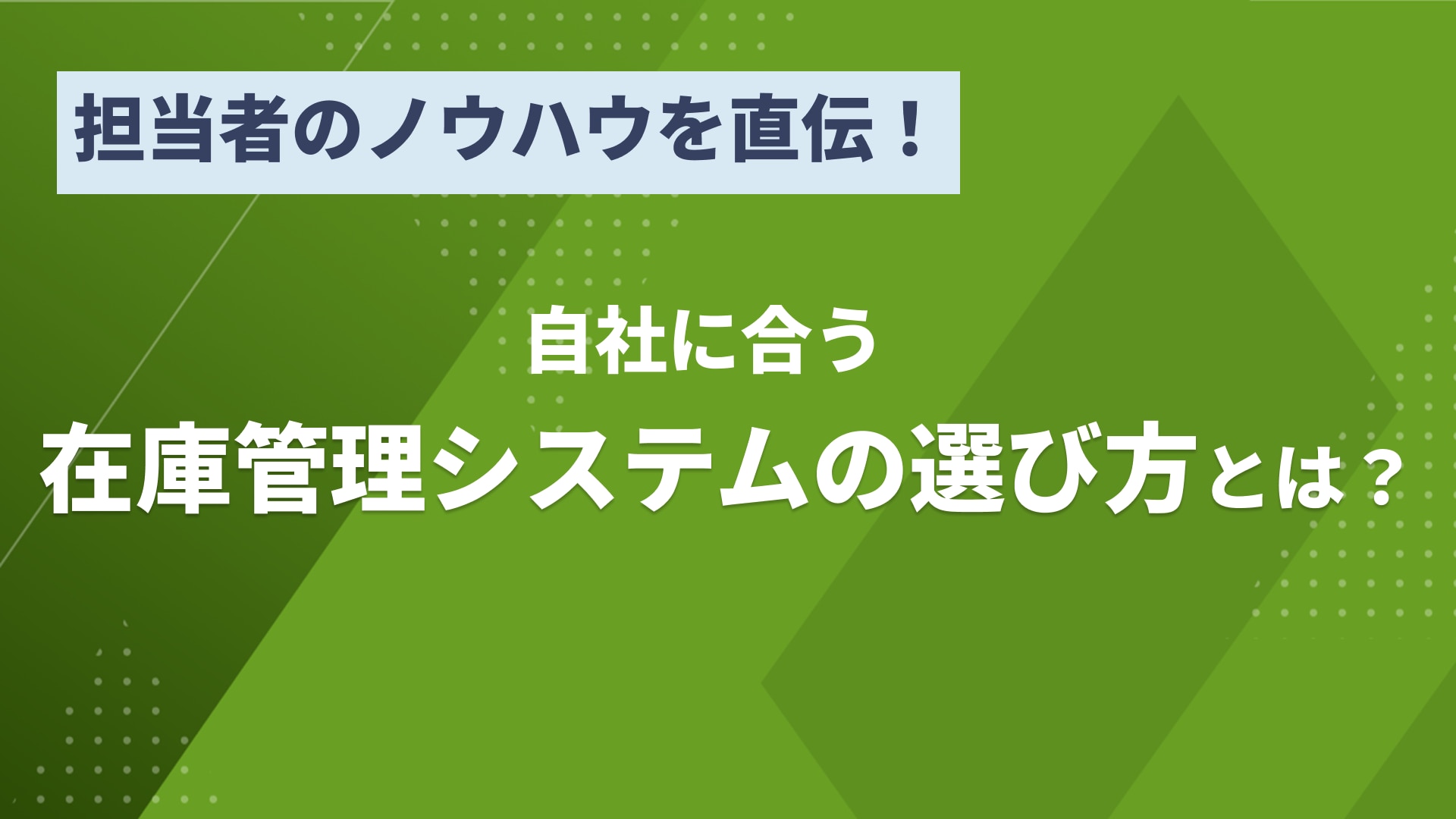
自社に合う在庫管理システムの選び方とは?
在庫管理に関する課題解決へ向けての考え方や方法を、在庫管理システムを提供する企業の担当者さまにお話しいただきました。同業務のDX化を検討する場合の「在庫管理システムを検討する方法」や、どんな在庫管理システムが合うのかを診断できる「チェックリスト式 在庫管理システム診断」 も合わせて情報提供していただいています。
今は、「たくさん作って置いておけば良い」という時代ではなく、正しい管理で在庫を最適化していくことが主流です。プロの目線の見解を、ぜひ自社の在庫管理業務に取り入れてみてください。
目次[非表示]
▼インタビュイー
受発注システム「TS-BASE 受発注」 担当者 田中さん(仮名)
入社後、システム開発部企画担当やロジスティクス事業部運営など、さまざまな業務に従事。あるプロジェクトをきっかけに受発注管理システムの開発を開始し、社内外問わず業務標準化へ向けた仕組みづくりを推進。その後、社内受発注管理・物流管理に活用しているシステムの外販を開始し、同事業を牽引している。
受発注システム「TS-BASE 受発注」 担当者 佐藤さん(仮名)
同サービス立ち上げ時から主要メンバーとして運営に携わり、顧客サポートやマーケティングなど、幅広い業務に従事している。実際に企業が抱える悩みや実状を長年に渡りヒアリングし、プロダクトの進化や運用フローの設計などへ生かしている。
在庫管理に関する悩みはどのような傾向があるのでしょうか?

田中さん:大きく分けて2つあると感じていまして、
1つ目は「在庫数が合わない」。
2つ目は「在庫管理が行えていない」です。
まず、「在庫数が合わない」について。
やはり、在庫数が合わないことに課題を感じる企業は多いです。この中には、受注した時に帳簿に書いてある在庫数と実際の在庫数が合わないという「リアルタイムの在庫数」も含まれます。その他にも、棚卸や商品入荷時にズレに気付くケースもあります。理由は異なっていても「どこでズレが生じてしまうのかが分からない」ことに頭を抱える担当者が多い印象です。
佐藤さん:2つ目の「在庫管理が行えていない」について。
1つ目と同じく「在庫数が合わない」状態ではあるものの、「在庫を管理する」状況になく、「どのように在庫管理をすればよいのかが分からない」というような、さらに前段階で悩む企業さまも一定数いらっしゃいます。
商品や社内備品の品目数は「大体〇〇品目くらい」とか、数量も「いつも100個くらいあるようにしているはず」というような感覚頼りになっていて、大変失礼ながら「社内規定で記録は残してはいるけど、あまり管理する必要性を感じていない」と思わざるを得ない状況も実際にあります。
あと、扱うモノによって意識が異なる場合もあって、顧客からの預かり商品など、「絶対ズレてはいけないモノの管理」は一定程度できているが、自社の備品になった途端にずさんになってしまう。「足りなくなったら作るか、買えばいいから」という補充が容易にできるものも、ぞんざいになりがちな印象ではありますね。
在庫管理の課題解決には、どのようなアクションが必要でしょうか?
田中さん:ステップがあると思っています。「在庫管理が行えていない」状態の場合、まずはエクセルシートで記録をすることから始めてみてください。1商品1行みたいなイメージで、「モノの出入りをしっかり管理する」意識をもって帳簿付けを行うことが最初のステップです。
帳簿付けを行っている企業で、しっかりとした管理意識を持っていたとしても、次の段階で「帳簿在庫と実在庫が合わない」という課題が出てしまいます。その課題意識から、エクセルシートでマクロを組んで、より詳細な記録をしていこうと工夫し、どんどん管理が煩雑になっている企業が多い印象です。または、エクセルシートをどのようにバージョンアップしていいのか分からず、未改善のまま運用を続けているという状況の企業もあります。
このような状態は、先述した「在庫数が合わない」という課題を抱く人が当てはまると思います。このような場合は、次のステップとして、在庫管理で見落としがちなポイントに目を向けてみて欲しいです。
在庫管理における転記や計算ミスでお悩みの方に向けて、それらを防ぐための在庫管理ツールをご紹介しています。あわせてご覧ください。
在庫管理で見落としがちなポイントとは何でしょうか?

佐藤さん:皆さんが目指している「最適な在庫管理」や「在庫の最適化」ができている状態はどのようなものかというと、
今、「どこに」「何が」「どれくらいあるのか」。
を、しっかり理解して管理できている状態です。これが見落としがちなポイントで、課題解決のネックになっている部分になります。
なぜ見落としてしまうのかと言うと、扱うモノによってポイントが異なる場合が多く、一概に「これをこうすればいい」と言えるものではないからです。なので、インターネットで調べても答えが出てこない。これを自身の目で見つけることは非常に難しいことではありますが、まずは「自社に特異なポイントがあるはずだ」と、認識することが大切です。
認識をしたら、今までの運用を思い浮かべながら、自社ならではのポイントを探してみてください。
例えば、
・廃棄など出荷以外の要因がある。
・不良品の管理が曖昧になっている。
・在庫の棚と在庫品の紐付け管理ができていない。
・複数箇所で同商品を在庫している。
・商品一つ一つの期限管理。
など、悩みの部分や自社商品にはこれが必須だと思う点など、思いつくままに挙げていきます。
田中さん:上記のポイントをふまえ、現在の管理方法をアップデートしてみてください。
私たちが提供する受発注管理システム「TS-BASE 受発注」では、「どの明細が分かれるのか」「どこの棚に何があるのか」「いつまでの期限のものが何個あるのか」「ロット違いで何個ずつある」などの管理ができる仕組みづくりをしています。それを、エクセルシートなどで管理できる工夫をすれば、現運用の延長戦上で課題が解決する可能性は高いです。
特に、「在庫商品に住所をつけてあげる」という発想をお持ちの人が少なく感じるので、商品を置く場所を決めて、その場所に番号を発番するだけでも、商品の在りかが分からなくなる問題は減ると思います。エクセルシートやアクセスなどでの管理を継続していくのであれば、このような「もう一歩上の視点」をもつ運用にしていくべきだと思います。
佐藤さん:ただし、エクセルシートのリスクは改めて理解しておいて欲しいです。システム化を検討する多くの企業担当者が問題視していたのは、「エクセルシートを活用した運用でのヒューマンエラー」の点でした。
例えば、各支店から毎月数十のエクセルシートがメールで送付され集計作業が発生している場合や、複数名でクラウド上のエクセルシートを運用している場合の同時アクセスや更新の問題、関数を崩してしまった場合の対処など、多くのトラブル事例を耳にしてきました。
エクセルシートでも、創意工夫をすれば高水準な在庫管理を実現することは可能だと思います。しかし、新しい要素を足したい場合や行を追加したい時に、エクセルのルールを知っている必要性や、ツールとしても脆弱性があることは理解しないといけません。
知識が豊富な社員が制作したシートを使う場合、再現不可能なくらいのエクセルシートになる場合もあって、業務がブラックボックス化してしまいます。そこまでのエクセルシートが必要になる業務であれば、システム化したほうが効率的な運用が実現できる可能性が非常に高いです。
在庫管理システムの導入を検討する時のポイントはありますか?

田中さん:少し前の話と重複してしまうかもしれませんが、「自社で扱うモノの特質や性質」「自分達の環境で何が必要でどのような管理を行いたいのか」を、整理して把握しておくことが大切です。
世の中には多くの在庫管理システムが存在していて得意分野が異なります。例えば、「液体や粉を扱っているから個数でカウントができない。重量で検品している」という場合、自社にとっては普通のことだとしても、れっきとした「特性や性質」です。この管理条件をクリアできる仕組みがもとより備わっていたほうが良いということになります。
また、「バーコードで商品管理をしている」「バーコードが付けられない商品を扱っている」なども該当します。前者はハンディの活用が必須になるので、その仕組みがあるのか。後者は、今現在の管理方法の整理や、商品名など文字情報を読み取るOCRという仕組みがあるので、それに対応できるシステムが選択肢になってくると思います。
佐藤さん:あとは「環境や管理」について。利用シーンや利用頻度は重要なポイントで、各社共通して該当するのは「入出庫の頻度」「商品数」など、ボリューム的な部分かと思います。事業規模が大きな場合や高額な製品になると、必要機能も異なってくるでしょう。
そして、「システムを利用する場所」も考慮する必要があります。スマートフォンやタブレットを使用して倉庫の一角で操作をしたいのか、使用する場所や人を限定したいなどで、必要な仕組みは異なります。
繰り返しにはなりますが、「自分達がどのようなモノを扱い、どのような運用で活用していきたいのか」をちゃんと整理することが大切です。そのためにも、「周辺業務部分も一緒に現在の運用の洗い出しを行って、問題点や改善点がないのかを点検してみること」が結構重要です。その上で、自社に合う在庫管理システムを選抜していくと良いと思います。
まずは基本的な知識から! 在庫管理システムの導入を考えているならこちらもご覧ください。
在庫管理とは? 課題解決と業務効率化を同時に実現する方法
自社に合う在庫管理システムはどのように選べばいいのでしょうか?

田中さん:私どものさまざまな経験から、在庫管理システムは大きく分けて4区分あると思っています。もちろん、その中でより細分化されていきますが、入口として「どれにあてはまるだろう?」と考えていただき、該当しそうな在庫管理システムの調査をして、問い合わせをしてみるのが良いと思います。
4つの在庫管理システム
➀「倉庫管理システム(WMS)一体型」在庫管理システム
②「ECサイト・通販特化型」在庫管理システム
③「小規模ビジネス向け」在庫管理システム
④「受注・販促物管理一元型」在庫管理システム
佐藤さん:4区分のネーミングは弊社が主観で決めたものなので、参考としお考えください。
まず、前項までにご説明した以下を書き出すなどをして可視化してみます。
・自社で扱うモノの特質や性質。
・自分達の環境で何が必要でどのような管理を行いたいのか。
・どのような運用で活用していきたいか。
・周辺業務部分含む、現在の運用の洗い出し。
その後、どの区分に当てはまるのかを検討し、可能であれば問い合わせをしてみて、「導入することで、現在の課題は解決できそうか」「システムを導入するメリットはありそうか」などを、ベンダーの人達に協力をしてもらって答えを出していくことで、在庫管理の課題解決の足掛かりになっていくと思います。
とはいえ…、「自社の在庫管理はどの区分なのか?」の判断が出来ないという人もいると思います。
そこで、どの区分に当てはまるのかが分かるよう、弊社がお客さまと商談した経験則をもとに「自社に合う在庫管理システムを診断できる“チェックリスト式 在庫管理システム診断”」を制作してみました。
無料DL:自社に合う在庫管理システムが分かる「チェックリスト式 在庫管理システム診断」
「在庫管理システム診断」の設問に沿って回答することで、前項4区分の在庫管理システムの中で、どの区分に該当するのかを診断することができます。それぞれの在庫管理システムの特徴や、どのような点に着目して、どのような効果が見込めるのかなどを、診断結果とともに簡単に説明させていただいております。
まだ在庫管理システムの導入は考えていない、時期尚早だと考えているかたも、エンターテイメント感覚で診断してみることで、新たな発見や業務の見直しにつながるヒントを得ることができるかもしれません。ぜひ気軽に試してみてください。