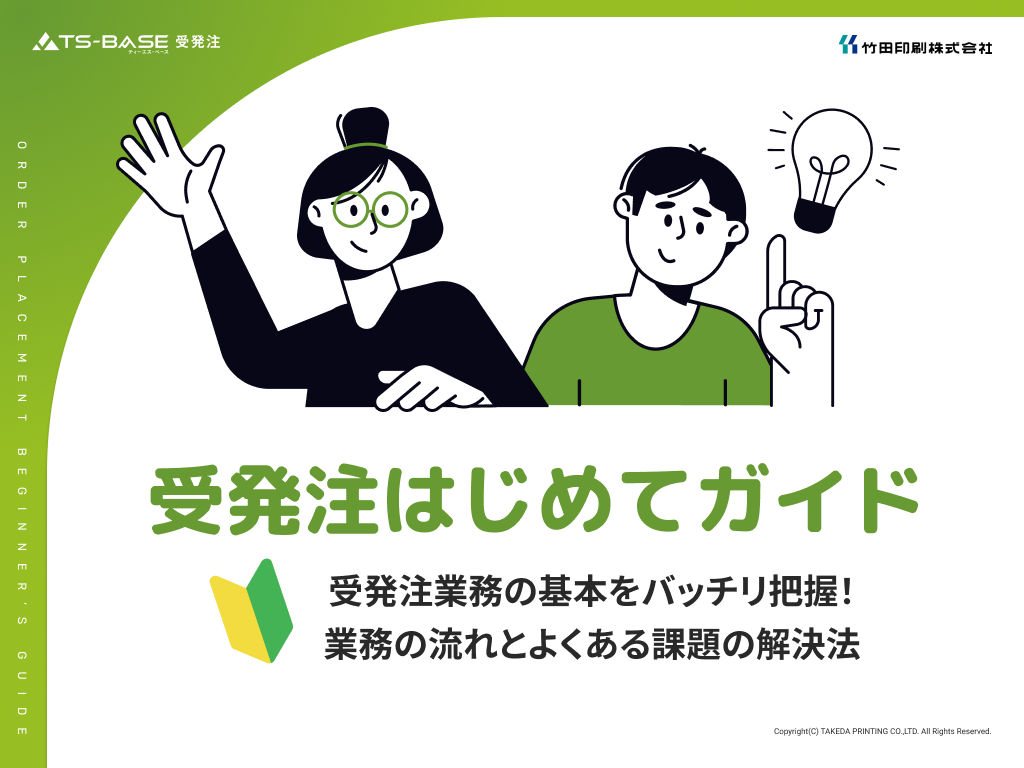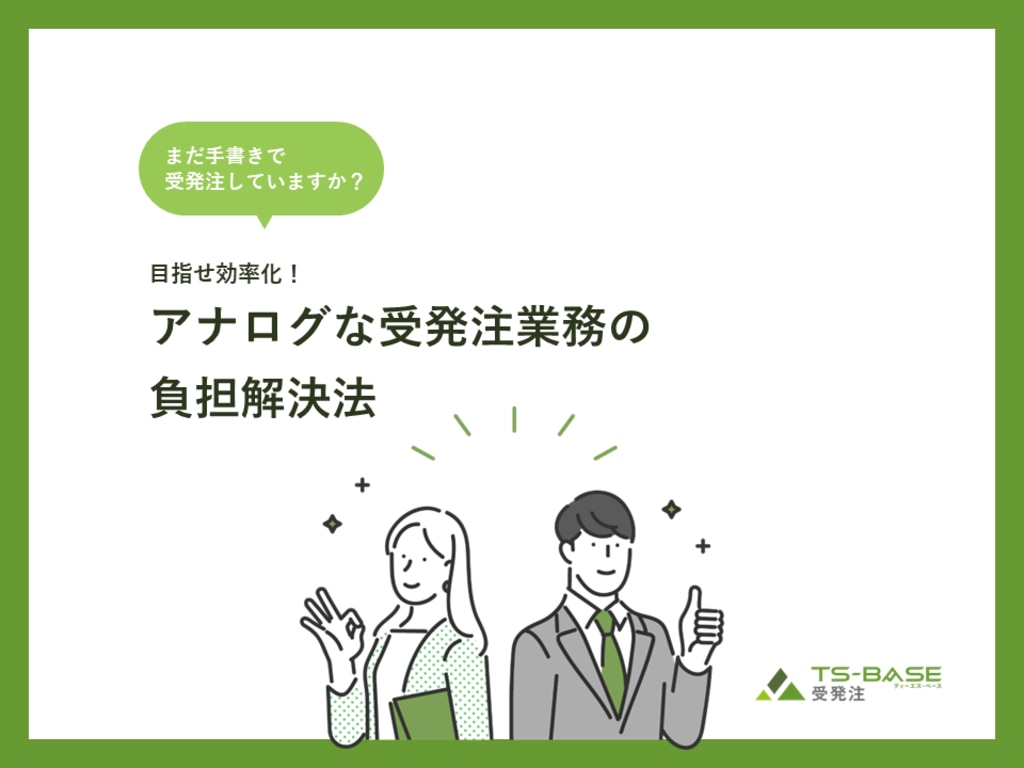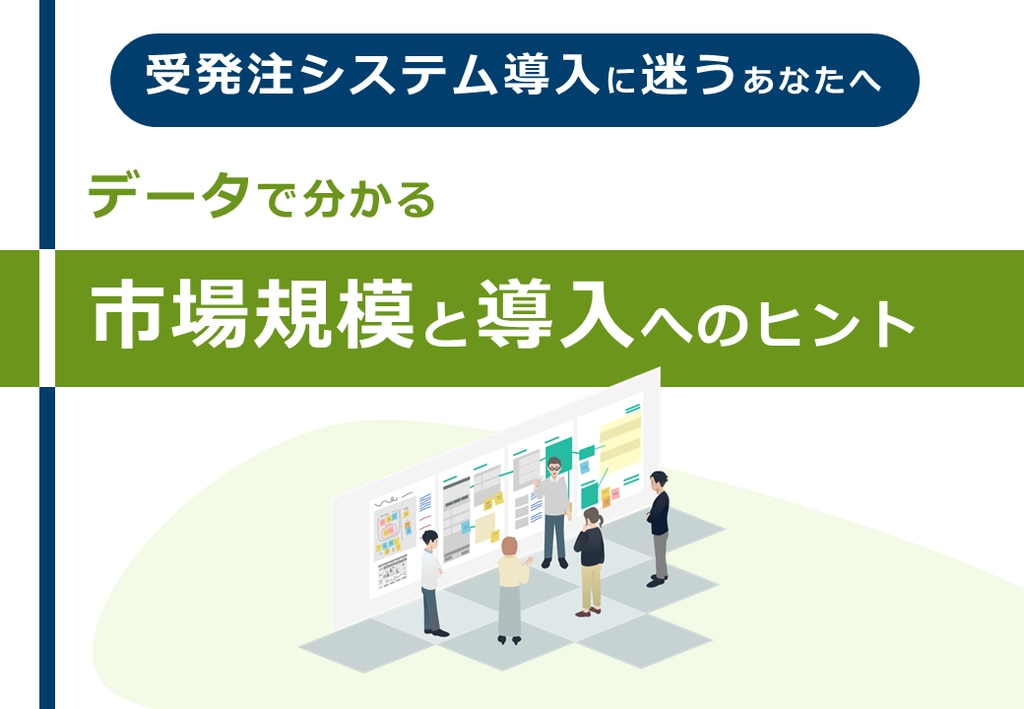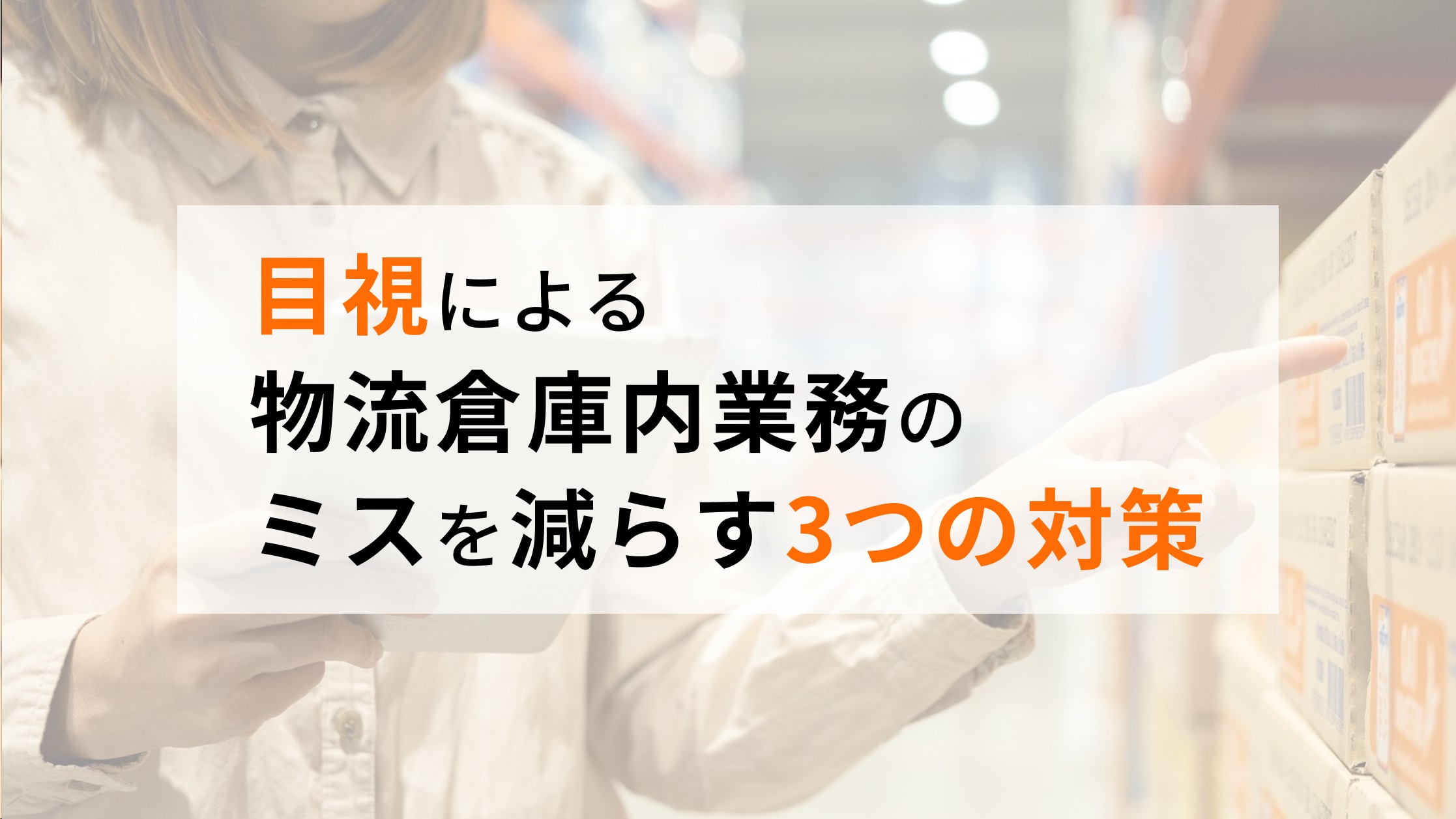
目視による物流倉庫内業務のミスを減らす3つの対策
人的労力が必要な場面の「目視確認」が発生する部分にフォーカスを当て、対策例をご紹介いたします。物流倉庫内の自動化が進む中でも、人間が行う業務は大切な役割を担っています。いかにミスを削減するのかを検討する際は、まず人が関わる作業を段階的にチェックしてみることをオススメします。日々の作業の一場面を改善することで、即座の効果を期待することも可能です。
今回は、人が視覚を使って判断する目視確認作業の効率化やミスの防止につながる対策をご紹介いたします。
目次[非表示]
物流サービスの質を高めるために、人的作業へ目を向ける

物流倉庫は、商品を製造する企業と商品を必要とするユーザーのハブ的役割を担い、迅速かつ安全なモノの流通に必要不可欠な存在です。日々多くの商品を扱う物流倉庫では、「入荷」「出荷」業務が占める割合は比較的多く、円滑な業務進行のために人員配置に頭を抱えるケースが見受けられます。
昨今、物流業界の人手不足の影響や即日配送などのニーズ変化から、サービスの質を担保するために多様な工夫が必要になっています。テクノロジーの導入で省人化を図ることは効果的ですが、導入検討やコストなどから即効性は期待できず、中長期的な目線が必要になってきます。
比較的短期間でサービスの質を向上させる考えかたとして、「人的作業へ目を向けてみる」があります。新たな仕組みを導入したとしても、人の手を介する業務は必ず発生します。スポットで対応をしてくれる人材を含め、いつでも誰でも一定のクオリティで業務ができる土台作りをすることで、サービスの質を高めていくことは可能でしょう。
さり気ない一場面でも、その作業を改善することで心理的安全性が確保されたり、その後の業務がスムーズになったりなど、好影響が拡大することもあります。「こんな些細なこと」と思わず、小さな改善を繰り返していくことで複合的に質の向上へつなげていくことは可能です。日々の業務内で感じた疑問や不満を軽視せず、目を向けてみることが大切です。
物流倉庫内の「目視確認」への対策

人が目で見て確認する「目視確認」は、物流倉庫内で多く発生しています。例えば、入荷作業では事前に共有される入荷情報と同じ商品が同数量で到着しているのか。出荷作業では、注文商品が正しくそろっているのか、破損などがないかなどの確認があります。物流倉庫に導入している仕組みなどの関係で、それぞれ発生する頻度や場面は異なれど、人の目を頼りにする業務は何かしら発生しているのは共通だと言えます。
今回は、この目視確認に着目をして、対策の例を提示していきます。
対策➀コードで管理をする
特に、バーコードや品番がない商品を管理する際に意識したいのが、「コードを発行する」ことです。
何かしらの理由で商品自体にバーコードや品番がない場合、商品名や外観などを目視確認するケースがありますが、担当者の感覚に左右される場面が多くなり、ミスを招きやすく非常に危険な管理方法です。例えば、外観が似ている商品を、「多分ここだ」という感覚で置いてしまうと、ピッキング作業へも悪影響が生じてしまうでしょう。
このような場合、物流倉庫で管理するためのオリジナルのコード(以下、商品コード)を発行して入荷から出荷までの業務を行うことで、共通項をもつ効率的な管理運営が可能になります。商品の仕入れ先で何かしらの管理番号がある場合は、それを活用してもよいでしょう。共通認識できる情報があれば、企業間のやり取りもスムーズになります。
実際の業務での活用イメージは、次項の「在庫棚」に関する改善策にて合わせてご紹介します。
対策②「棚番」を基準に在庫棚を管理する
商品を在庫する場所(以降、在庫棚)を管理する「棚番」の活用で、在庫管理やピッキング時の目視確認の精度向上が見込めます。

棚番とは、倉庫の在庫管理スペース内における住所の役割を果たす番号です。それぞれの商品在庫を置く在庫棚に番号を発行し、商品コードと紐づけて管理を行うことで、さまざまな場面での目視確認や管理業務を円滑にする効果があります。先述したコードと合わせた活用イメージの一例は以下です。
◆入荷
入荷情報と実際に入荷した商品を目視確認で照らし合わせ、発行した商品コードと棚番情報が書かれた紙を在庫棚へ貼り、その場所へ商品を在庫していく。在庫数の管理は商品コードを基準に行います。
◆出荷
棚番の情報をもとに在庫棚を探します。棚に貼ってある紙と、ピッキング情報に記載された棚番と商品コードを目視で確認した後、商品の外観(商品名など)を見て、必要数量をピッキングしていきます。
棚番がない場合、「あそこら辺にあった」という感覚で探したり、スポットで業務にあたる人は、在庫棚を何度も往復して探したりなど非効率的な動きが多くなります。棚番と商品コードという2つの情報を目視確認することは、出荷業務を正しく安心して進行できる裏付けになるため、慣れない作業への戸惑いを抑えることが可能になります。
対策③在庫の残数確認を行う
出荷商品のピッキングが完了したら、「在庫棚に残された商品数を確認する作業」を行うことで、目視確認ミスのリカバリーや、正しい業務進行が行われているのかの確認を行うことができます。
作業方法は、全てのピッキングが完了した後「帳簿上の在庫数から、当日のピッキング数を引いた数量が実際に在庫されているのかを確認する」内容になります。同作業を以降は「残数チェック」と記載します。残数チェックは、大きく分けて2つの効果が期待できます。
1つめの効果は、「ピッキングが正確に完了しているのかの確認」になります。ピッキングは人が目視で行うことも多く、間違いも発生しやすい作業です。残数チェックで商品在庫数が正しければ、その日の出荷に必要なピッキングは正しく行われたという裏付けになります。注文ごとの商品を目視で確認する際のリスクも減るため、さまざまな業務のWチェックのような役割も担います。
2つめの効果は、「在庫数の確認」です。帳簿と実際の在庫数を照らし合わせる作業になるので、残数チェックは正確な在庫管理ができているのかも確認できる作業です。
それぞれの商品確認には、時間も人的労力もかかり、「目視作業でもある残数チェックはミスを生むのでは?」という懸念があるかと思います。その場合、確認方法や在庫の置きかたに工夫を加えると解消できる可能性があります。考えかたの一例として、「9000の在庫がある冊子」を例にご説明いたします。
この冊子は、1ケース4000入りの箱で入荷をしています。基本的に、在庫棚に保管をする際は箱のまま保管をします。現在、在庫は9000あるので、「2箱(8000)と端数の1000」が在庫されている状況です。この場合、「端数の1000」の置きかたにルールを設定すると残数チェックが行いやすくなります。

ルールの例えは、「100や500などの単位で上下交互にテレコ状で重ねていく」「目視で分かりやすい形で10単位ごと紙をはさむ」などが挙げられます。残数チェックは、この端数分を目視で確認することで、スムーズに作業を行うことが可能です。どのような単位が最適なのかは、入荷時の箱の中の状況や注文数の傾向などで決定すると良いでしょう。
残数チェックの効率化は、ピッキングの効率化にも直結します。数量を目視で確認しやすい土台作りをしておくことで、各作業の効率化や正確かつスピードある運用が実現できる可能性が高まります。
ピッキングや残数チェック作業について、実際に竹田印刷株式会社が提供する物流サービス「TS-BASE 物流」の現場で行っている工夫をこちらの記事で紹介しています。ぜひあわせてご覧ください。
番外編:物流倉庫の備品管理に「目視確認」を活用
安全な倉庫運営に欠かせないキーワードとして「異物混入への対策」があります。物流倉庫では、基本的には余計なモノは持ち込まないことが鉄則ではありますが、必需品とされるモノの管理も徹底して行うことが求められています。この管理に「目視」を活用するのは有効です。

このように、業務に使用する備品置場を可視化しておくことで、紛失にいち早く気付くことができます。この他にも、個人が使用するペンの数をルール化するなどの対策は混入防止策として効果があります。
省人化・省力化が進む昨今ですが、そのために導入する仕組みを管理するのは人間であって、人の手を介する業務は減ったとしても無くなる訳ではありません。人は五感を使い、その人が正しいと思う基準で判断を下します。一人一人が自社の基準に沿った正しい判断ができるよう、ルール作りや啓蒙活動は常に実行していく必要があります。
今回ご紹介した「目視」に関しても、共通ルールや正しい判断ができる環境整備を進めることで、ミスが少ない物流倉庫運営を目指すことができます。ぜひ、自社の環境に当てはめて考えてみてください。